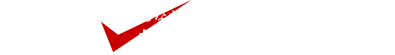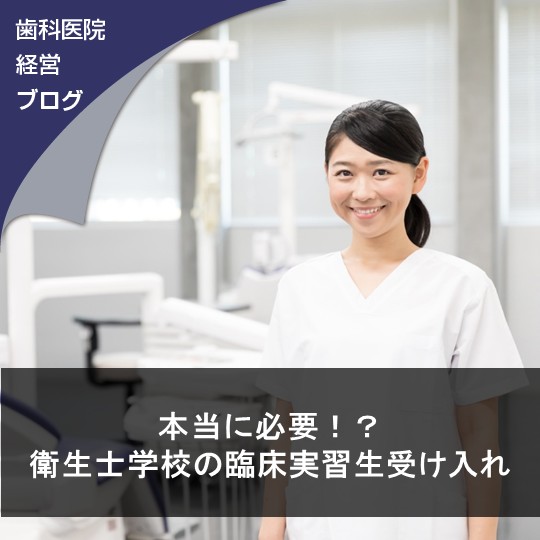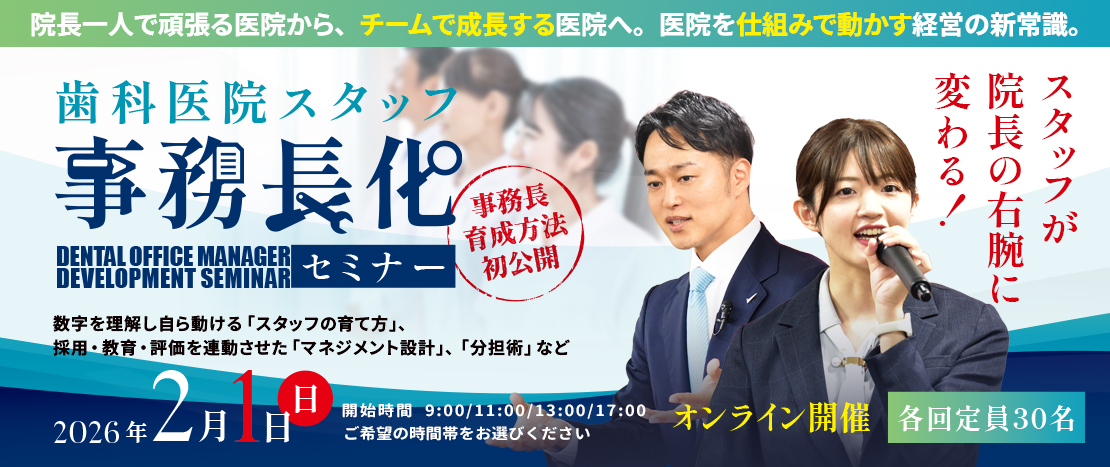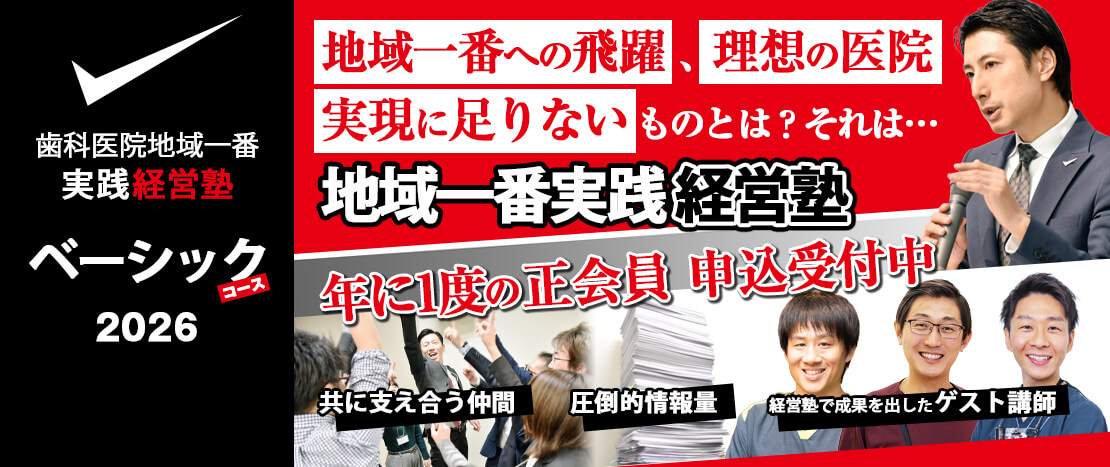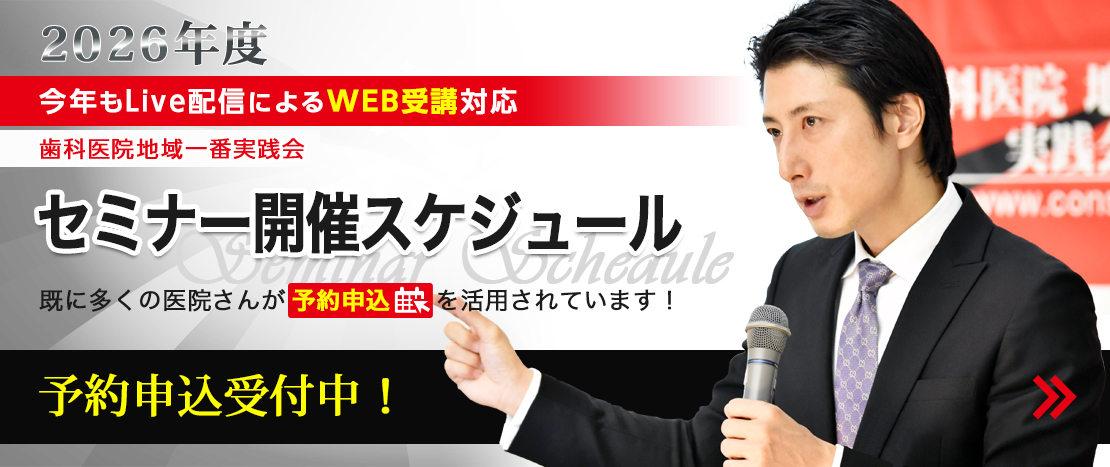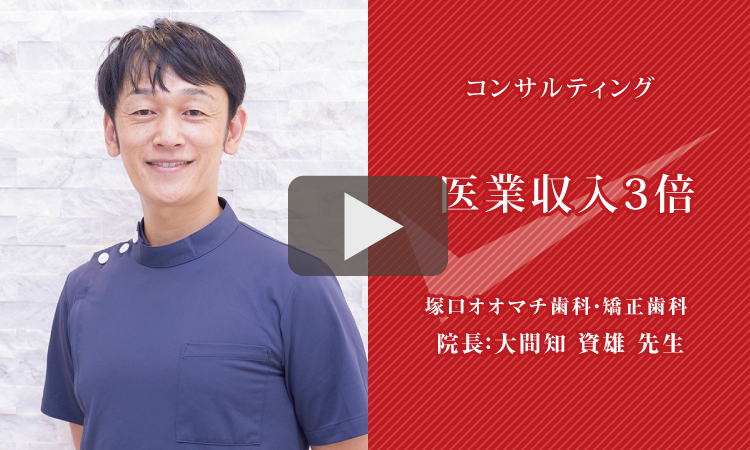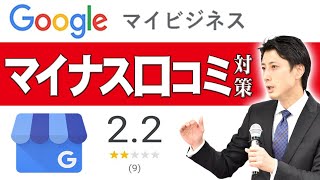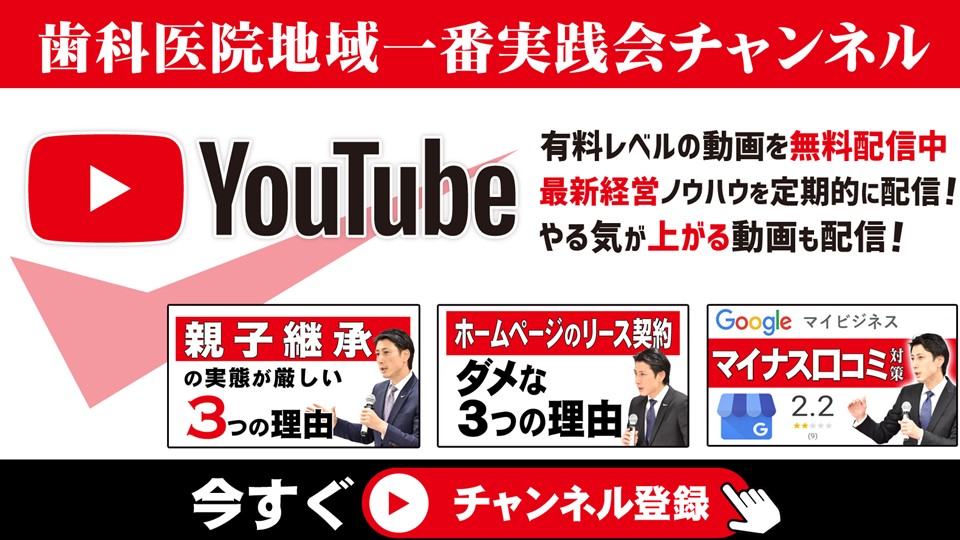このブログは約 9 分で読めます
皆さん、こんにちは!
歯科医院地域一番実践会の井ノ上です。
突然ですが、皆さんの医院では歯科衛生士の臨床実習施設として登録していますでしょうか?
登録していない医院様は、早急に登録に向けて話を進めることをおすすめします。人手不足の波が押し寄せている最中、数少ない採用ルートを見過ごしていることは、間違いなく中長期的に医院の採用状況に影響を及ぼします。採用難につながりかねないでしょう。
採用を制する医院が経営を制する
「今は人が揃っているから大丈夫」「臨床実習先にならなくても採用できている」と現状に甘んじていると、いつか足元をすくわれる時がきます。
医院の経営が上手くいっている時こそ、将来への備えや起こり得る課題に目を向けて、今のうちに対策を講じていくことが大切です。
臨床実習先になることが、そして、臨床実習先として的確な受け入れを行うことが、採用を制する、そして医院の経営を制するといえます。
ただ、また臨床実習先として登録されていない医院、登録したいけど何をすればいいか分からない医院もあるかと思います。最低限すべきことをお伝えしますと、“衛生士学校との関係づくり”、これに尽きます。
そりゃそうですね。学校が信頼していない医院へは、大事な学生を送り出したいとは思いません。安心して実習を任せられる、さらに、就職の候補先として学生にも経験をしてきてほしい。そんな想いが学校側にはあります。
そう、“実習先=就職候補先”なのです。多くの実習生が、その実習先にそのまま就職します。すべての学生が実習先に就職するわけではないですが、第一候補に入ることは間違いありません。
人の行動における心理的プロセスとして「AIDMAの法則」というものがありますが、実習を受け入れることは、すでにAttention(注意)、Interest(関心)の段階をクリアしていることになります。実習先になっていない場合は、その学生にまず医院の存在を知ってもらう、そして、興味を持ってもらうために、求人サイトの掲載など様々な取り組みが必要になります。莫大な時間と労力がかかるわけですが、実習先になっているだけで、その過程をスキップできます。それだけで、他院とは大幅な差をつけることができるわけです。
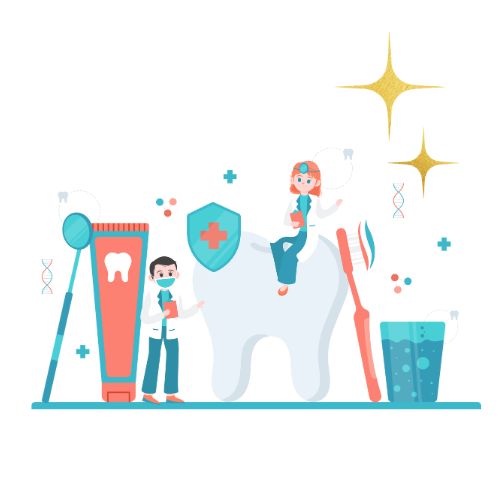
実習先になることは大きなアドバンテージ
歯科衛生士の有効求人倍率は約23倍と言われていますので、23医院の中で1名しか採用できない計算になります(※日本歯科衛生士会のサイトを参照)。
倍率23倍とは、23人で一斉に100メートル競争をして、1位になるような厳しい戦いです。その中で臨床実習先となっていれば、自分ひとりだけ50メートル地点からスタートするぐらいのアドバンテージを得られているようなものです。
まずは、そのアドバンテージを得ることが競争を勝ち抜く上で必須事項になります。
衛生士学校との良好な関係構築を目指して、卒業生を連れて学校への定期的な挨拶を行うことや学校の非常勤講師として教鞭に立つ機会を探ってみるのも良いでしょう。
歯科医師会の会合にもしっかりと参加して、周囲の先生方とのコミュニケーションを維持していれば、ふとしたタイミングで思いも寄らないところから講師の依頼が来ることがあります。
私の担当している医院の院長先生は、出身大学のつながりから衛生士学校の講師を任されたことがありました。そこから、実習先の受け入れ、そして実習生の採用につなげられました。
このように学校との関係を築けると、必ず臨床実習先としての話が持ち上がります。
とは言っても、なかなかきっかけを作れない医院がほとんどかと思いますので、地域によっては複数の学校があると思います。まずは、医院で勤めているスタッフの中で卒業生が多い学校からアプローチしてみてはいかがでしょうか。
実習生受け入れの失敗事例
いざ実習生を受け入れるにあたって、やりがちな失敗例があり、
大きくは「教育体制による失敗」と「マネジメント状態による失敗」の2つのパターンが想定されます。

「教育体制による失敗」は、一言でいうと“放置プレイ”です。わりと多くの医院でそうなってしまっていますが、実習生で何もできないからと、担当もつけず、カリキュラムも設定せずに、見学だけをさせてしまっているケース。体制的に人が足りてなくて、実習生の面倒を見る余裕がない、そもそも教えられるスタッフがいないなど、理由は多岐にわたります。
もう1つの「マネジメント状態による失敗」は、いわゆるマイナススタッフが在籍している状態での受け入れは、基本的に上手くいかないことが多いです。お局スタッフが幅を効かせて、パワハラまがいの指導をするケースは結構あります。
社会の厳しさを教えるという正義感を持って指導しているつもりかもしれませんが、実習生にただただ恐怖心を与えるだけにすぎません。
医院にとってマイナスはあってもプラスの要素は一切ないでしょう。
また、「あそこの医院は厳しい院長がいる」「やばいスタッフがいる」などと悪評が広がり、レッテルを貼られてしまったら、その年の採用だけにとどまらず、数年に渡ってその学校からは応募は来ないと思った方がいいでしょう。学校での評判は、私達が想像している以上にインパクトがあります。
実際に私の担当しているクライアントで、1人のマイナススタッフの影響で学校中の学生に悪評が知れ渡ってしまい、そのマイナススタッフはすでに退職して医院にいないにも関わらず、今も根も葉もない噂が残っています。一度、立ってしまった悪い噂は、そうそう消えません。
そういった意味で、実習生の受け入れる場合は慎重に判断する必要があります。上手くいけば、採用力の大幅な向上につながりますが、下手に体制が整っていない状態でやると、採用どころではなくなるリスクがあります。
採用は評判が命
良くも悪くも、採用は評判が命です。特に地元の衛生士は、一定のコミュニティがあるので、その中で医院の情報が出回っています。転職時には、「〇〇医院ってどう?」と周囲の衛生士に確認した上で応募の判断にしています。そのコミュニティ内での医院の情報をどのように構築していくかの意識が必要になります。
実習先での印象は、そのコミュニティ内での情報を大きく左右するわけです。その時に就職につながらなくても、その実習生に実習を通して良い印象を与えることができれば、いずれは違った形で成果にあらわれると思います。
採用面接はマーケティングの一種とお伝えすることがあります。
要は、面接に来た方が採用にならなくても、その方は未来の患者様、また患者様を紹介する方になり得るので、不採用者だとしても無下には扱わないようにということです。
実習生の受け入れは最優先事項

実習生の受け入れも同じことがいえるのではないでしょうか。
その実習生が、もし出来が悪く、何もできない学生だとしても、その実習生の同級生、先輩、また知人、周囲のコミュニティ内の衛生士が未来の採用候補者である可能性は十分にあります。その実習生が、学校内で大きな影響を持つ学生かもしれません。その後の医院の評判に大きく影響を与える存在かもしれません。
そう考えて、実習生1人ひとりの受け入れにおいては全力で対応する。その気持ちが医院にとっては必要なのだと思います。
今回は、衛生士学校の臨床実習生受け入れの必要性、そして受け入れの際の医院の心構えについてお話しました。採用を制する医院は経営を制します。採用を制するために、新卒の採用ルートをしっかり確立することが望ましいといえます。
効果的な臨床実習生の受け入れを行い、継続的に医院の理想に合った新卒の採用につなげていきましょう。