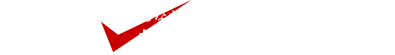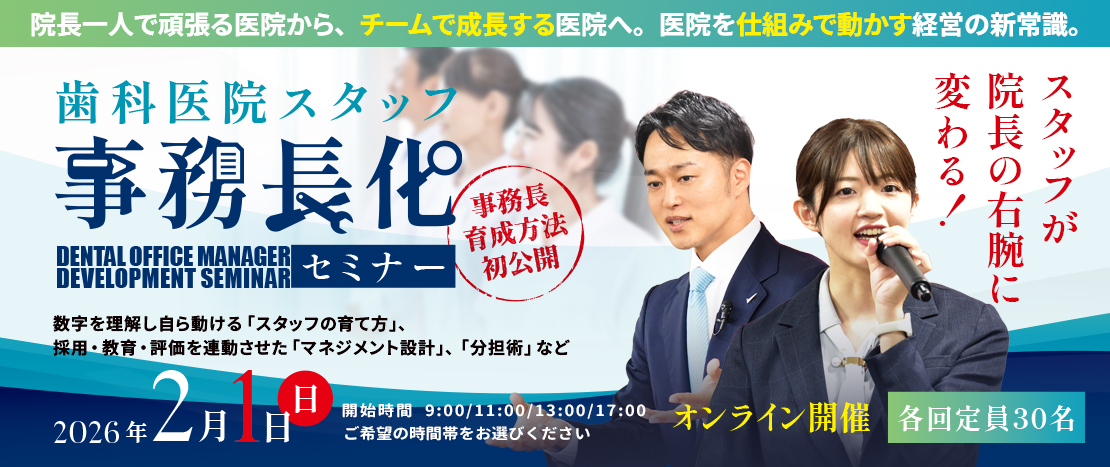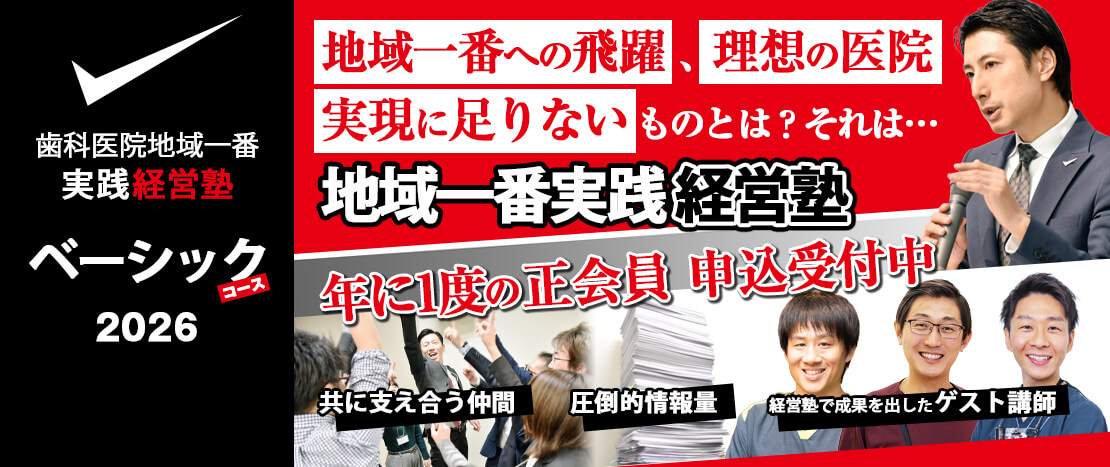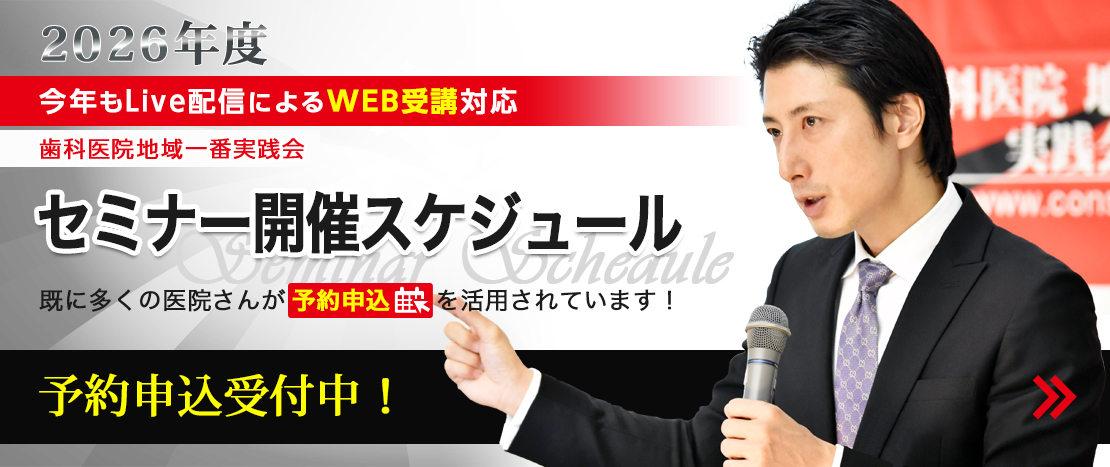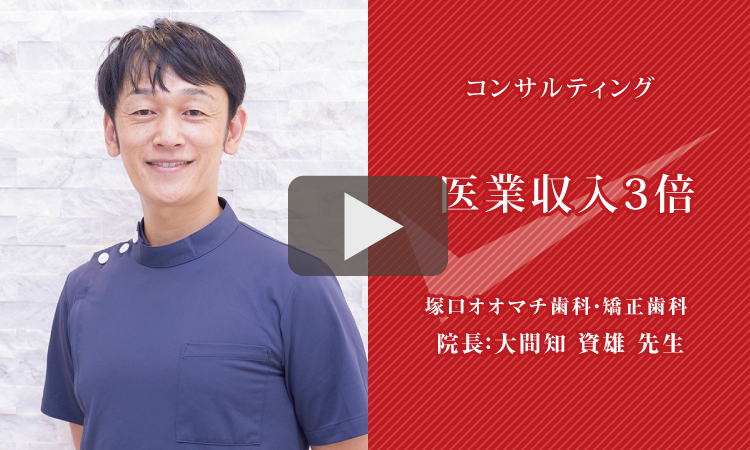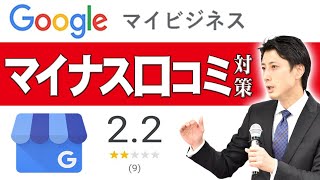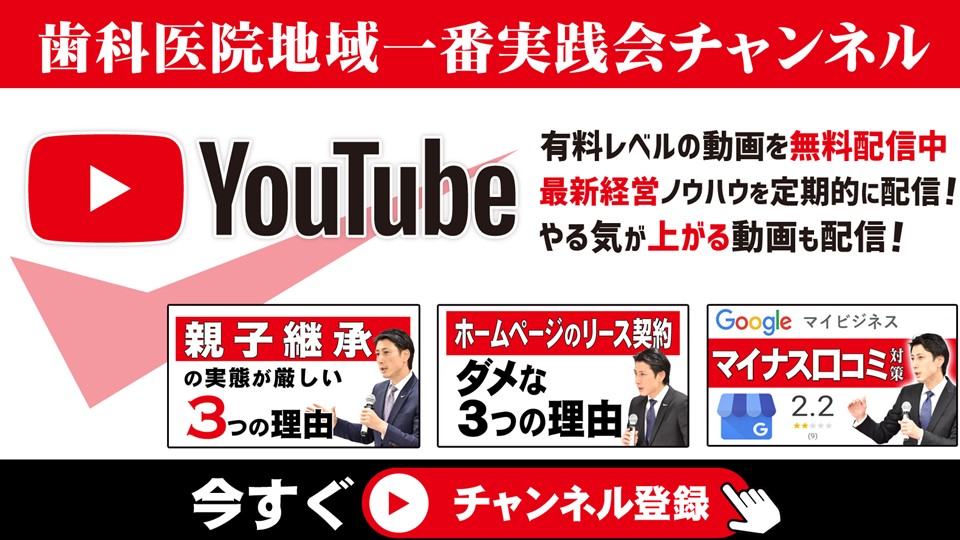このブログは約 7 分で読めます
こんにちは!経営コンサルタントの山ノ内です。
今回は2025年6月20日に厚生労働省が公表した「歯科衛生士による浸潤麻酔の実施に向けた研修プログラム(例) 」について考えてみたいと思います。
と、その前に、考えの前提にもなる骨太方針にも触れたいと思います。2025年6月に公表された令和7年度の骨太方針(「経済財政運営と改革の基本方針」の通称)では、少子高齢化と労働人口の減少に対応すべく、医療・介護分野における「タスクシフト・タスクシェア」がしっかりと明記されています。歯科医療の現場においても例外ではなく、業務の効率化と人材の有効活用が急務となっていることを日々のコンサルティング業務の中で実感しています。
そんな中、注目すべき動きの一つが、前述した歯科衛生士による「浸潤麻酔」実施に向けた制度設計の動きです。厚生労働省は特定の条件下で歯科衛生士が浸潤麻酔を行うことを可能とする教育カリキュラム案を公表しました。
考え方にもよりますが、これは、職務充実を推進する一つの大きなきっかけになるのではないかと思います。
浸潤麻酔のカリキュラム公表とその背景を考える
今回のカリキュラム案は、既にいくつかの団体が独自の研修を行い、実施を推進している歯科衛生士の浸潤麻酔に関して、国としても安全性と有効性を担保しつつ歯科衛生士の業務を拡張することを目的としているものと考えます。(ただ、推奨はしてないとのことですが。)具体的には、一定の教育・訓練を受けた歯科衛生士が、歯科医師の指示・管理下で限定的(歯肉縁上及び歯肉縁下の歯石除去、ルートプレーニング時の疼痛除去)に浸潤麻酔を行えるよう学校のカリキュラムに組み込むという内容です。
このカリキュラムの導入は、以下のような実態や複数の課題を背景にしているのではないかと考えています。(仮説も含みます)
- 既にいくつかの団体で研修が実施され、臨床で実施されていること
- 患者数の増加
- 歯科医師の人手不足
- チーム医療推進の必要性 etc
これらに対応するには、単に人を増やすのではなく、「限られた人材を最大限に活かす仕組みづくり」が必要です。これこそが骨太方針が掲げる「タスクシフト・シェア」の核心なのではないでしょうか。
歯科衛生士のモチベーション向上とマズローの欲求5段階説
今回のような歯科衛生士による「浸潤麻酔」実施といった職務充実は単なる人員不足対策にとどまらず、スタッフのモチベーション向上にもつながると考えています。

ここで参考になるのが、アメリカの心理学者マズローが提唱した「欲求5段階説」です。この理論では、人間の欲求は以下の5段階に分類されるとされています。
- 生理的欲求(食事・睡眠など)
- 安全の欲求(職の安定など)
- 所属と愛の欲求(仲間・チームへの帰属感)
- 承認の欲求(評価・昇進)
- 自己実現の欲求(能力を発揮し、成長したいという願望)
今回のような職務拡充は、特に4〜5段階の「承認」および「自己実現」の欲求を刺激すると考えます
「自分のスキルをもっと発揮したい」
「歯科医師と対等にチーム医療として貢献したい」
上記のように考える歯科衛生士にとって、浸潤麻酔の実施は大きなやりがいにつながるのではないでしょうか。実際の現場でも「やってみたい」という声は少ないと肌感としてあります。
歯科医院経営に与えるインパクトと戦略的な取り組み
歯科衛生士の職務充実は、医院経営に以下のようなポジティブな影響を与える可能性があります。
- 治療効率の向上
⇒歯科医師が集中すべき処置に専念できる
- 予約枠の拡張
⇒人材活用の最適化により1日あたりの処置数が増える
- 収益性の向上
⇒ユニット稼働率の最大化、技術単価のバランス最適化 - 人材定着率の改善
⇒やりがいのある職場づくり
もちろん、すぐにすべての医院が導入できるわけではありませんし、すべての医院で実施した方が良いとは全く思っておりません。安全面・教育面の整備、医院ごとの方針設定が前提となります。
ですが、時代の流れを先取りして準備を進める医院は今後の競争環境において優位に働くと思いますし、勝ち抜ける可能性は高いと思います。

変化を見据えた上での2つのアクション
今後の変化を見据えて、以下の体制・文化の醸成は必要になるかと考えます。
- 職務拡充の情報収集と院内共有
⇒制度改正の動向等を理解し、歯科医師・スタッフと情報共有・議論する場の設定 - 人材投資を経営戦略に組み込む
⇒給与だけでなく、教育投資や職務設計に注力し、スタッフの能力と意欲を引き出す文化づくり
最後に
骨太方針が示す大きな潮流の中で、歯科業界も今、大きな転換点にあります。今回のような歯科衛生士の職務充実は、スタッフのモチベーション向上、治療の質と効率の向上、さらには医院全体の成長に直結する、非常に重要なテーマです。
昨今では強制的な教育・指導がしにくい社会です。自己研鑽するか、しないかを本人に任せる組織も少なくないと思います。置かれている状況において仕方のない場合もあると思います。ただ、自由度が高い分、頑張る人は頑張るし、頑張らない人は頑張らない、どんどん格差が拡大していく傾向もあるのではないでしょうか。勿論、それは歯科だけでなく、医療分野全般、もっと言えば日本社会全体かもしれませんが。
変化を恐れず、未来に向けて準備を進める歯科医院、そしてそれができる環境・文化を醸成させた歯科医院こそが、地域に選ばれ続ける存在となると私は考えています。
歯科医院経営の新たな戦略
業務の効率化と人材の有効活用をお考えなら
こちらのセミナーも是非!
↓↓↓
歯科医院受付ZERO実現セミナー
https://www.consuldent.jp/seminor/zero-reception/