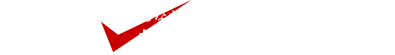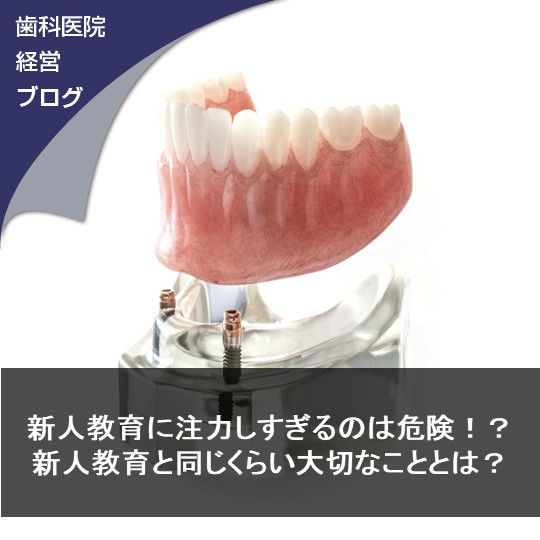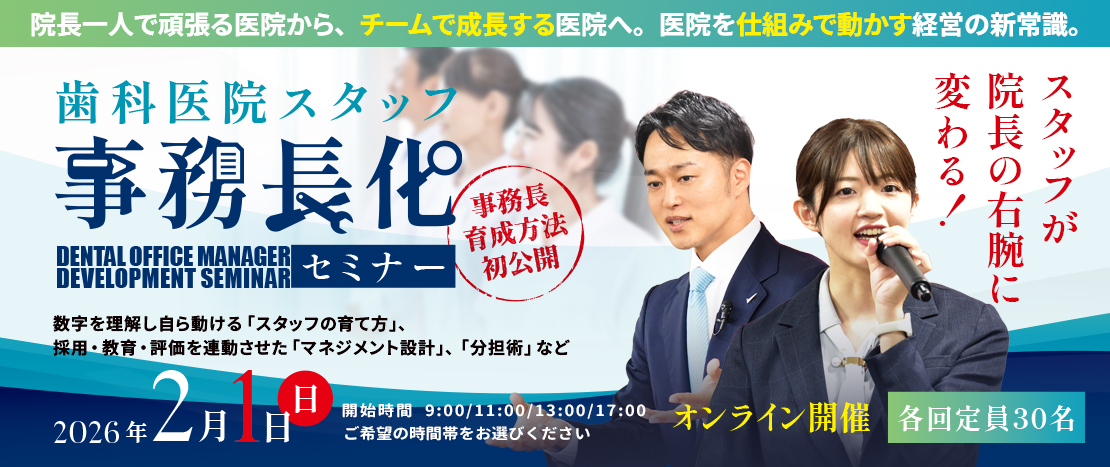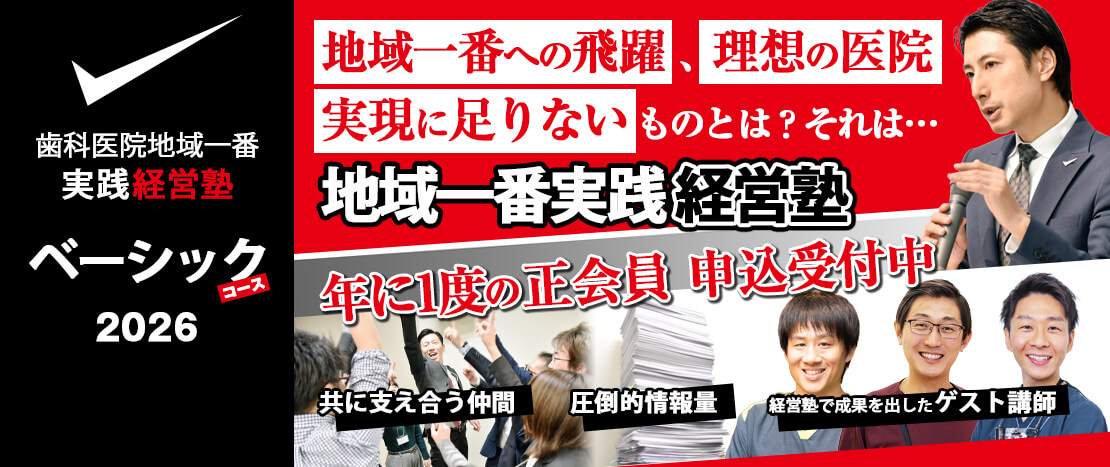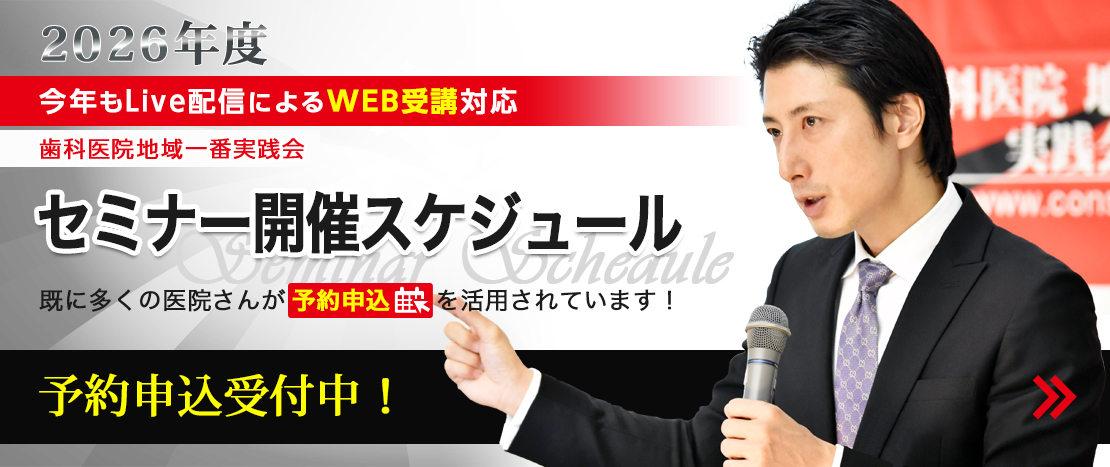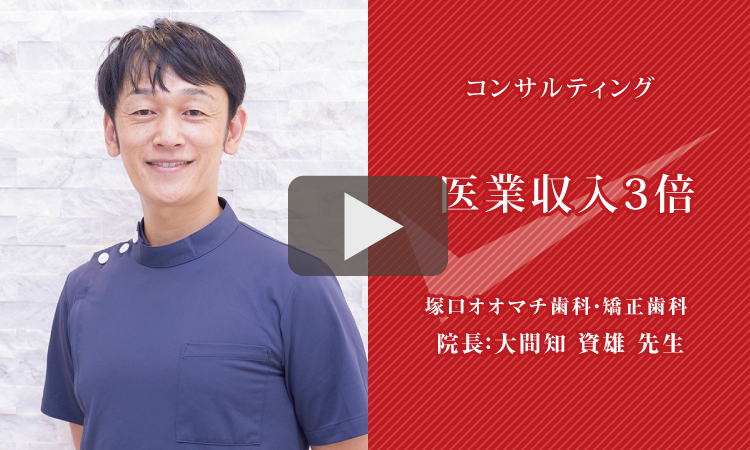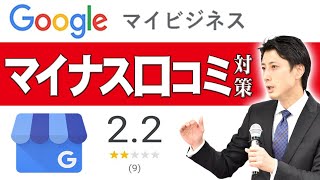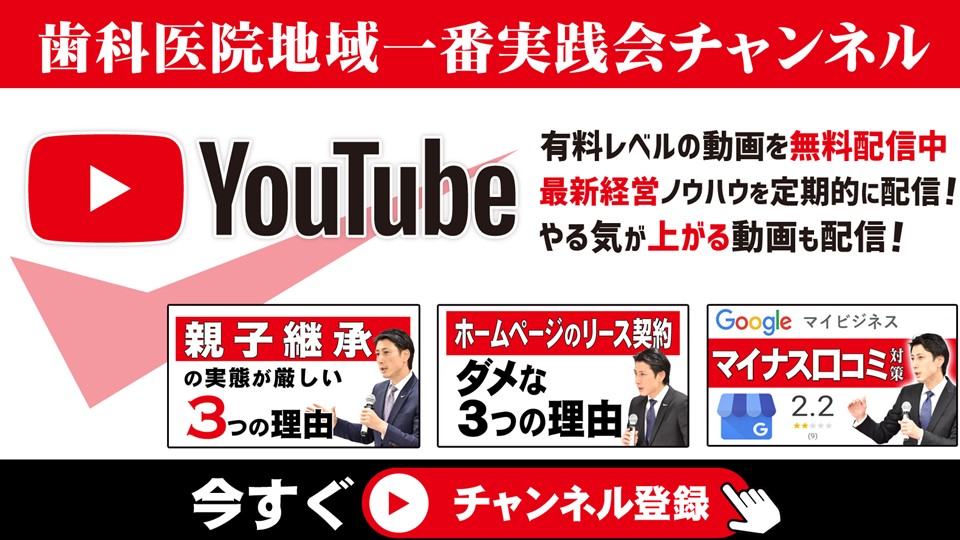このブログは約 7 分で読めます
皆さん、こんにちは!
歯科医院地域一番実践会 コンサルタントの平社雄一です。
多くの医院で4月に新人が入社し、絶賛新人教育をしている頃だと思います。毎年、新人が入って1,2ヶ月くらい経つとよく起こるのが、「新人が育つ前に、教える先輩が疲れ切ってしまった。。教育担当者を降りたいです――」
皆さんの医院でも過去このようなことが起きたことがある、もしくは現在まさに起きているのではないでしょうか?

全方位の採用活動をして、多額の採用費をかけ、ようやく採用できた新人スタッフ。そのため新人教育に注力するのは勿論ですが、並行して教育担当者が心身共に疲弊していくということが多くの医院で起きています。
新人を採用し、ここから医院を更に成長させていくぞ!と意気込んでも、既存スタッフが教育担当者になったことで疲労困憊になり、不満を持ってしまっては本末転倒です。
今回は、新人教育ではなく、教育担当者に焦点を当て、教育担当者のケアについて記載していきます。
今、教育担当者が陥っている状況とは
現在、教育担当者は「診療・指導・フォローアップ」という3つの業務を日々こなしています。診療しながら今行っていることを1~10まで事細かに伝え、自分の業務を後回しにしてまずは新人の指導に時間を使っています。
その後、ようやく溜まっているカルテ記載をする等の自分の仕事を片付け帰路につく、、気が付けば4月から毎日残業が続いている、、、ということが多くの医院で起きています。
また、新人教育をするのは2年目~3年目のスタッフが多いです。
自分の臨床もままならないのに、こんな実力で後輩に教えていいの?という不安にかられ更に疲労が増す。このような悪循環になっていないでしょうか?
疲弊を招く8つの理由
ここからは具体的に教育担当者が何に疲れているのか、どんなことに不満を持ちやすいのかを記載します。
- 新人がメモを取らない
同じ説明を何度すれば良いのか?何回も言ってるんだからメモくらい取ってよ。覚える気ないの?というストレス。 - 反応が薄い
うなずきや返事が少ないと、理解度が読めません。「響いていないのかな?」と不安が重なり、声掛けのトーンが自然と強くなる悪循環も。 - 教える時間がない
教育の時間が確保されていないので診療中に教えることが出来ない。かといって昼休みや診療後に残って教えるのは新人も教育担当者も嫌。 - 院長の無関心
「教育は任せたよ」で新人教育を放置してしまう。新人がきちんと育つかを教育担当者に委ねられているという歪なプレッシャー。チェア4,5台の医院でよく起きています。 - 時間的プレッシャー
アポイントが詰まっている中での“つきっきり指導”は物理的に無理が生じます。患者様対応に追われ、新人は見学や片付けがメインになりがち。急患対応が重なると、スケジュールが雪崩式に崩れがちです。 - 評価の不公平感
「新人が褒められ、私は評価されない」。教育手当を支給されていないことが多く、教育担当者は頑張り損と感じやすい。 - 関係性ストレス
年齢が近いと注意しづらい、年齢差が大きいと距離が縮まらない――立ち位置によって悩みは変わります。 - 教え方が分からない
ほとんどの教育担当者は“教え方”を学んだ経験がありません。何をどうやって教えたら良いの?状態です。
教育担当者を守る2つのポイント
1,ダブル担当
理想は新人1名に対して教育担当者1名がつきっきりで教えるという育成スタイルです。基本的にまずはこのスタイルでうまくいくように試行錯誤すべきです。
ただ、どうしても教育担当者が1名だと疲弊してしまう場合もあります。
その場合は教育担当者を2名にするのも有効です。2名体制なら心理的肉体的負担が半減するからです。
但し、必ず注意しなければいけないことがあります。
レクチャーする人が複数人になることで、
「A先輩とB先輩の言っていることが若干異なる」
これがほぼ確実に生じます。この違いにうまく対応できる新人スタッフは良いのですが実際少なく、大体は先輩の言っていることが違うと戸惑ってしまうのです。
そのため、事前に新人スタッフに「やり方に迷ったら〇〇さんに確認して」と確認先を明確にしておきます。
新人スタッフからの確認が合った場合は教育担当者間で共有し、やり方を統一するということを繰り返していくことが重要です。
2,院長面談のルーティン化
定期的に(初月は週一、2ヶ月目以降は隔週や月一回くらいの頻度が目安)面談で
「今どこが大変?」「新人の反応は?」と具体的に質問していきましょう。教育担当者が困っていることを傾聴し、必要に応じて業務調整を即断即決してあげることが重要です。
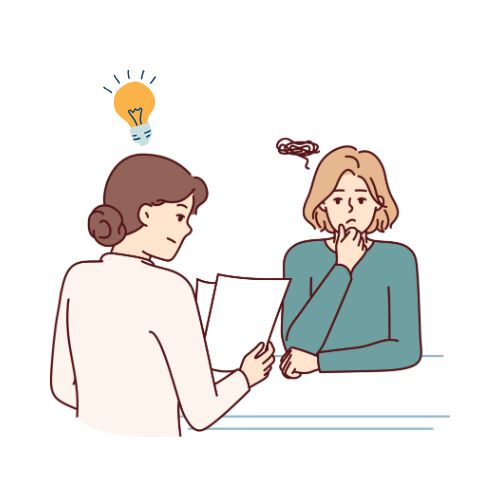
規模が大きな医院では、必ずしも院長が面談する必要はありません。
過去教育担当を経験している先輩スタッフが、面談してあげるでもOKです。
教育担当者になる中堅スタッフ向けのセミナーもありますので、是非ご活用ください。
まとめ
新人教育のゴールは、新人を一人前にすることではありますが、副産物として、教育担当者が新人教育を経て、新人以上に成長することです。
一方で新人教育において、教育担当者が疲弊しきってしまうと診療に大きく影響し、医業収入にも直結します。また、それを見た周りのスタッフは「教育担当者にはなりたくない」というマイナスなイメージを持ってしまいます。
新人を早期で独り立ちさせることは勿論重要ですが、それと同じくらい教育担当者をケアし、教育担当者も育成していければ、医院はまた大きく一歩前進するでしょう。
弊社には新人スタッフ向けの1DAYセミナーもありますので、こちらも是非ご活用ください。