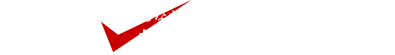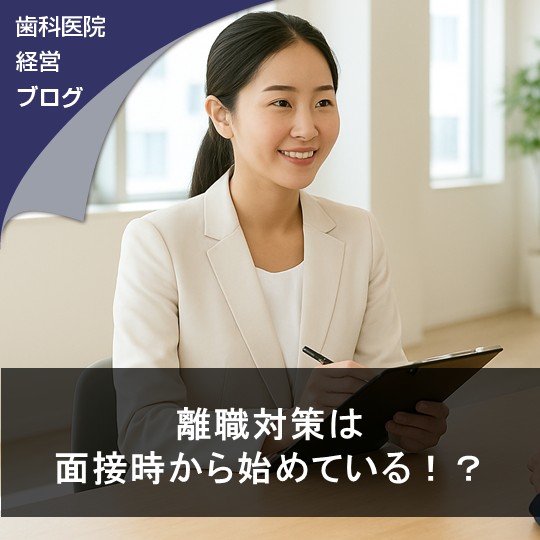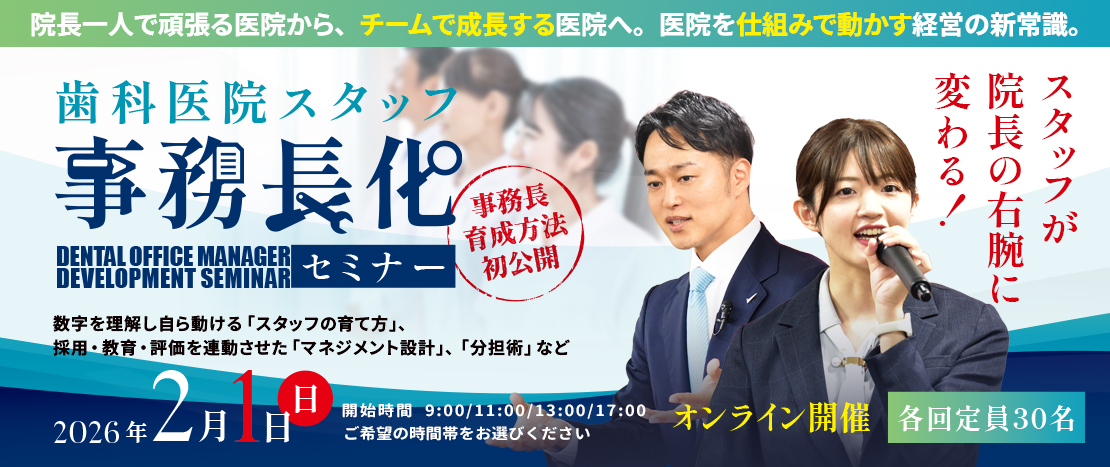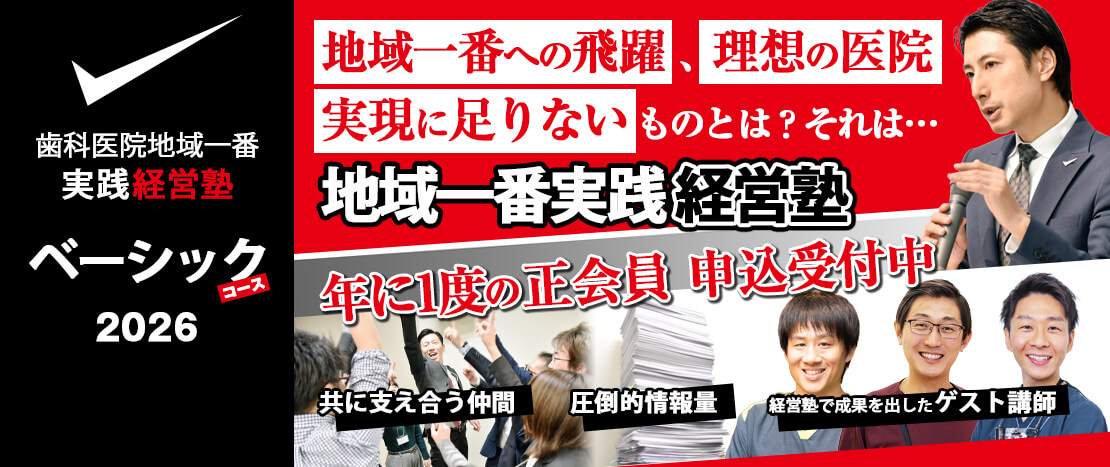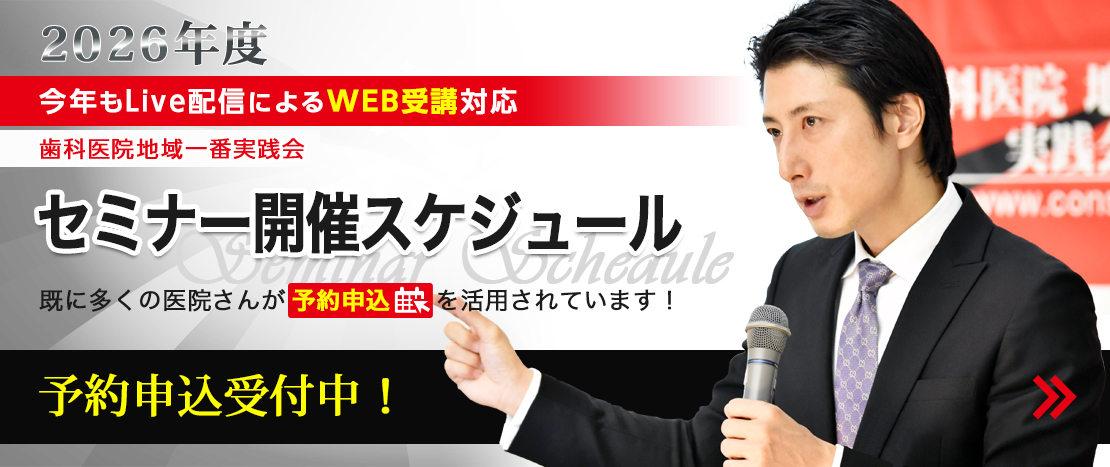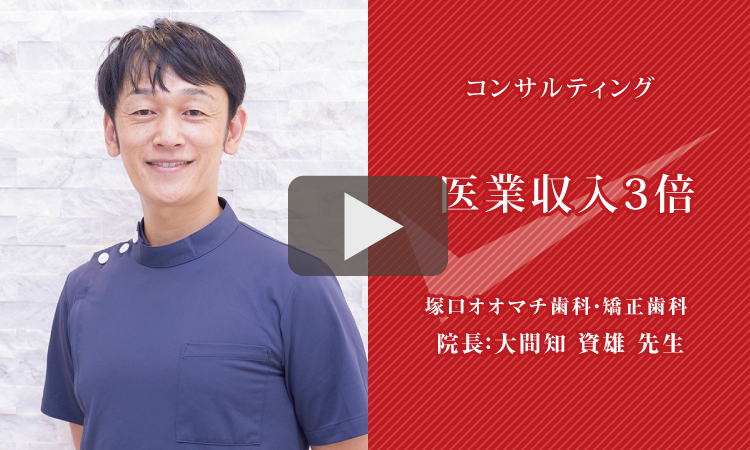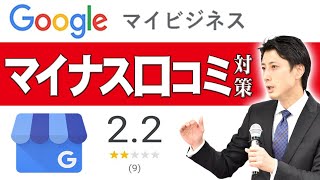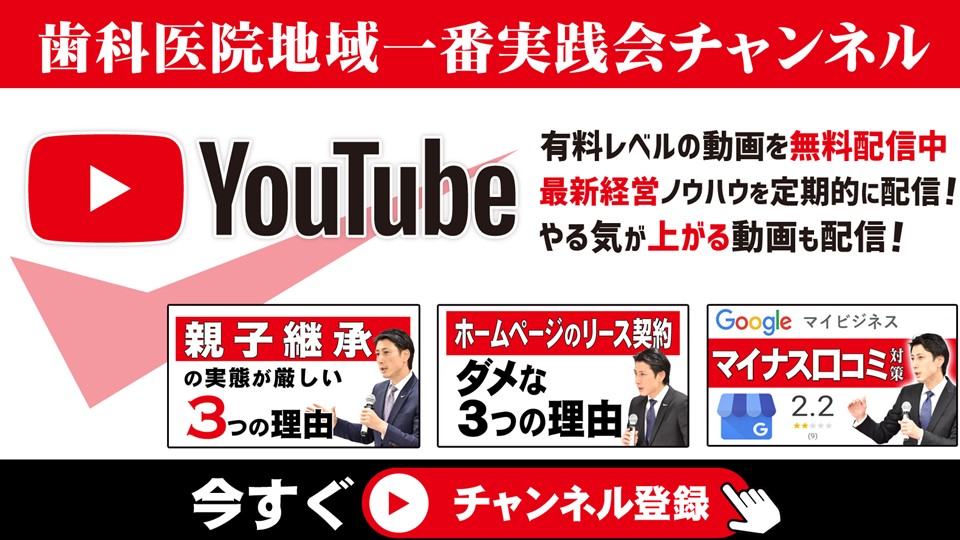このブログは約 6 分で読めます
皆さん、こんにちは!
歯科医院地域一番実践会 コンサルタントの平社雄一です。
人は本能的に変化を嫌います。特に職場では、前触れのない「突然の変更」が不安や不信を増幅させ、優秀なスタッフの離職につながりがちです。だからといって変化を止めるわけにはいきません。
大事なのは、変化を“想定内”にしておくこと。
中長期計画を事前に話すだけで、同じ出来事でも“急な変更”ではなく“予定どおりの進捗”に置き換わり、離職の芽を摘むことができます。今回はは、歯科医院でリアルに起こりうる離職を生む変化の事例と、それを防ぐための伝え方・運用のコツをお伝えします。
人はなぜ変化を嫌うのか
多くの人は基本的に現状を維持しようとします。
なぜなら、変化が起こることで、忙しくなる、考えて動かないといけなくなる、漠然とした不安が襲ってくるからです。また、予告なく起きる変更は“損をしそう”という感情を呼びやすく、抵抗が生まれます。職場環境の変更に対しても同様で、事前の説明や納得度が低ければ、抵抗を生んでしまうのです。
加えて、人は「失う痛み」を「得る喜び」より強く感じます。そのため、たとえ良い結果につながる改善でも、今の慣れたやり方・時間の余裕・評価の安定を失うかもしれないと感じた瞬間に防衛反応が働きます。
さらに、先が読めない、自分はうまくやれないかも、決めるプロセスに参加していないという三つが揃うと、反発は一気に強まります。
「変化を起こさない」ではなく「変化と感じさせない」
変化に伴う離職の対策は、「変化をさせないように、医院の成長を諦める」では勿論ありません。
医院の成長は無くてはならないものではあり、経営上必須です。
ポイントは医院の成長を入社前の段階で “想定内化”にさせることです。
面接時に「何が・いつ・どれくらい」変わるかを具体的に説明し、頭の中に未来の当たり前として仮置きしてもらうことが重要です。
そして、その時がきたタイミングで「予定どおりです」にさせるわけです。
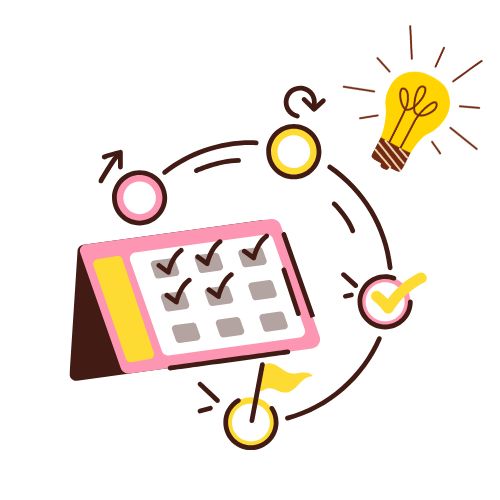
中長期計画を話すだけで離職が減る理由
事前に中長期計画を共有すると「ずっと院長が言っていたことだから」という意識が醸成され、同じ施策でも“急な変更”ではなく“計画の実行”に変わります。これが非常に大切なのです。
面接前は勿論、月1のミーティングや、キックオフのたびに定期的に院長が今後の計画を語るというのが非常に大切なのです。
“中長期計画”は難しくない
「中長期計画」と聞くと難しく感じますが、シンプルでOKです。
1年後:チェアが1台増えている。スタッフはDHが+1名、DAが+1名。最終受付は17:30で固定。1日の来院数は◯名。
3年後:チェアは合計◯台。スタッフ数は総勢◯名。1日来院が◯人(新患◯/再初診◯)。医業収入は保険で◯◯、自費で△△、リコール率◯%。
これくらいでも良いのです。
スタッフさんが、チェア台数、スタッフ数、1日の患者数を想像できれば最低限OKです。
“伝え方”
面接の段階では、「1年後にチェア+1、3年後に◯台。来院◯人規模。ただし終業は現状維持。役割は徐々に広がっていくけど、ごくごく普通のこと」という将来像を最初に伝えます。
入職時のオリエンテーションでは、開業時から現在までの医院の成長に関して、そして今後の計画について明確に説明します。
また、月1回ミーティングしているのであれば、数字の確認と共に毎回今後の計画に関して言っても良いくらいです。実際に私のクライアントでは毎回今後の計画についても話しています。
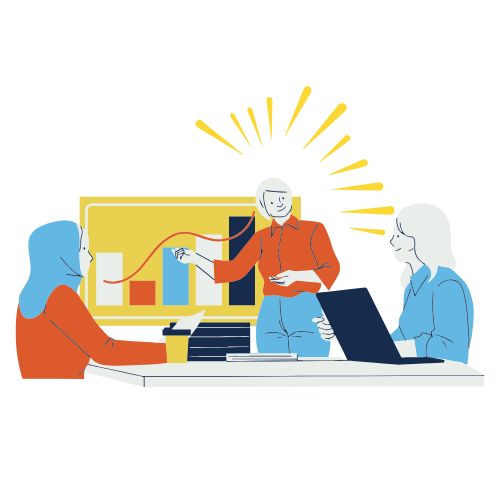
まとめ
離職の決意は、大事件よりも小さな“突然”の積み重ねです。たとえば、アポイントの枠を縮めることや、評価の基準を変える、診療の流れを変える——医院の成長のための変化だったとしてもスタッフが“突然の変化”と感じてしまうプロセスだと不要和音は起こります。
対策は、変化を止めることではありません。変化を“想定内”にすることです。面接の段階で「1年後はチェア+1、3年後は◯台・1日◯人」という将来像をはっきり伝える。
さらに、月1回の短い共有で「次に何を、いつ、誰にどう影響するか」など、具体的に知らせる。これだけで、スタッフは心の準備と生活の調整ができ、同じ施策でも“急な変更”ではなく「予定どおり」として受け止められます。
そして、院長が同じ内容を繰り返し、同じ言葉で伝え続けることが重要です。スタッフが「前から聞いていた話だ」と感じれば、驚きは薄れ、抵抗は小さくなります。結果として、辞めにくい職場ができあがり、日々の診療も安定します。医院の成長をスタッフにとっての“当たり前”にしていく——この積み重ねこそが、離職を防ぎ、患者さんに選ばれ続ける組織をつくる近道です。