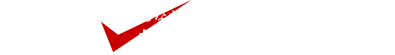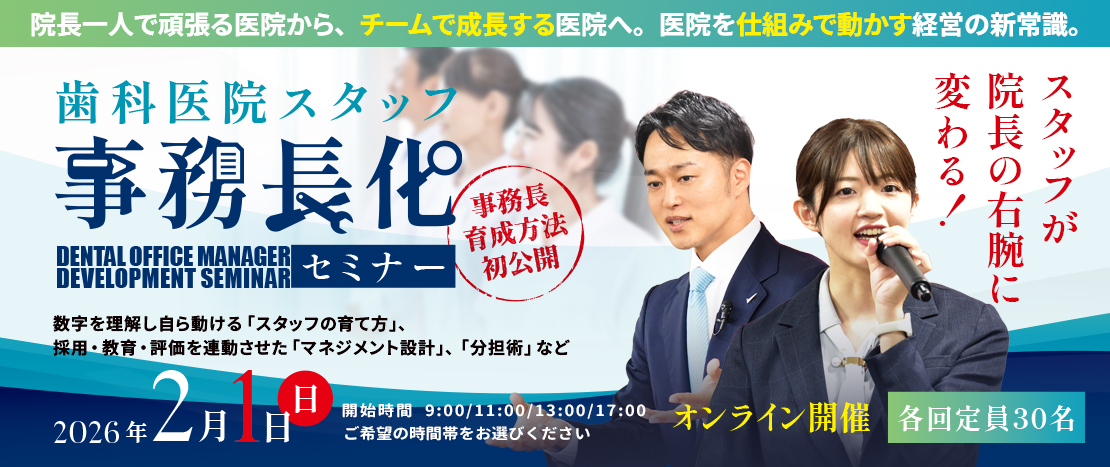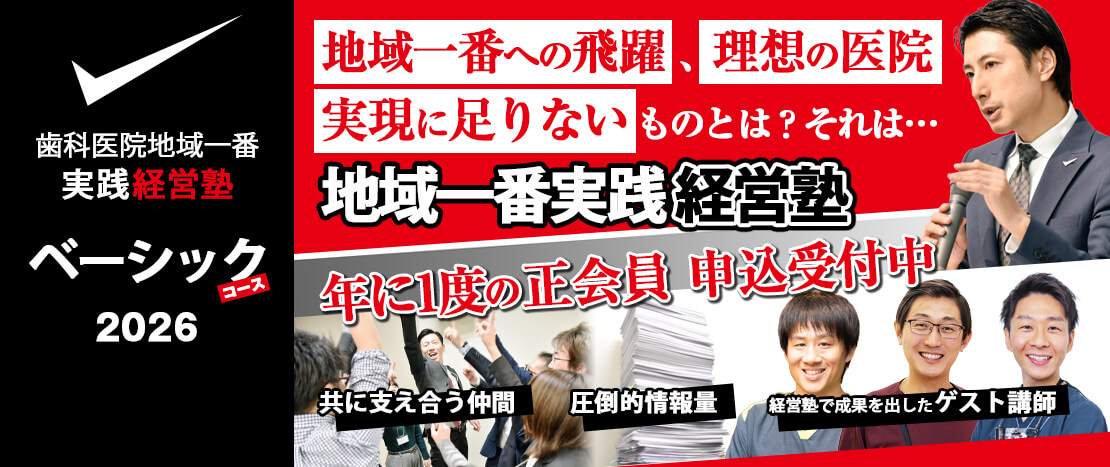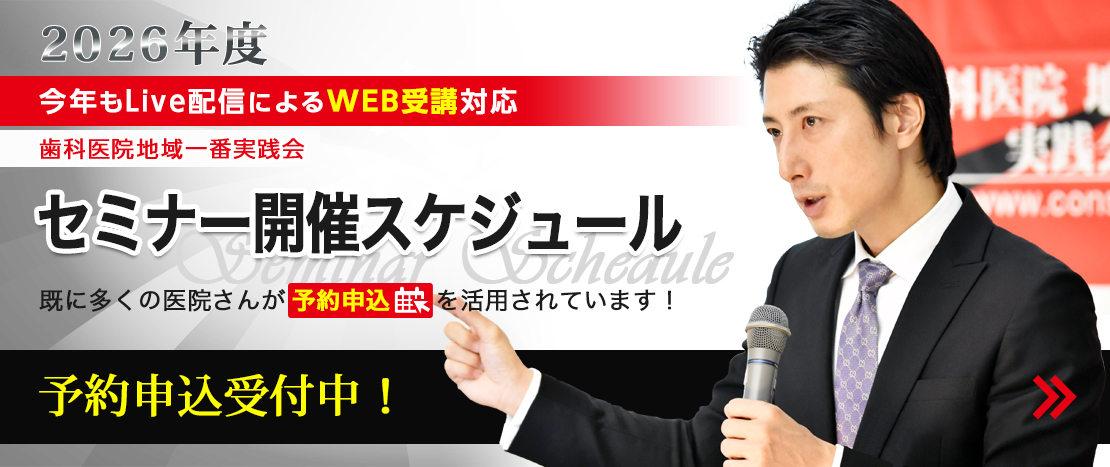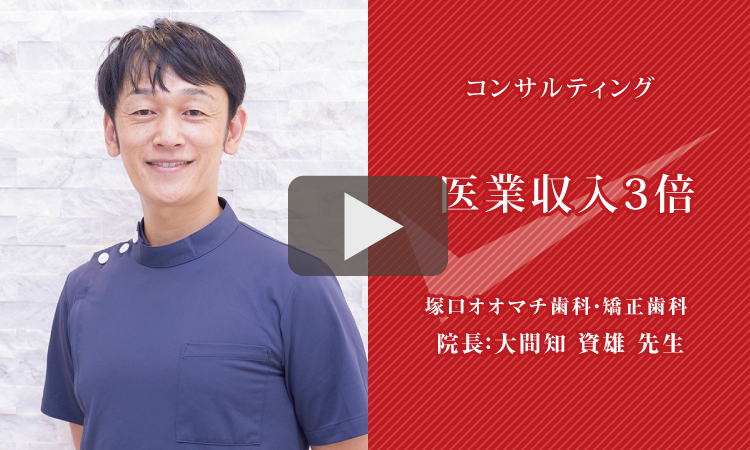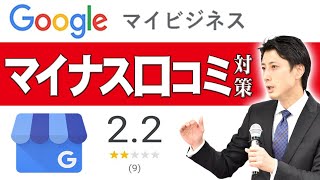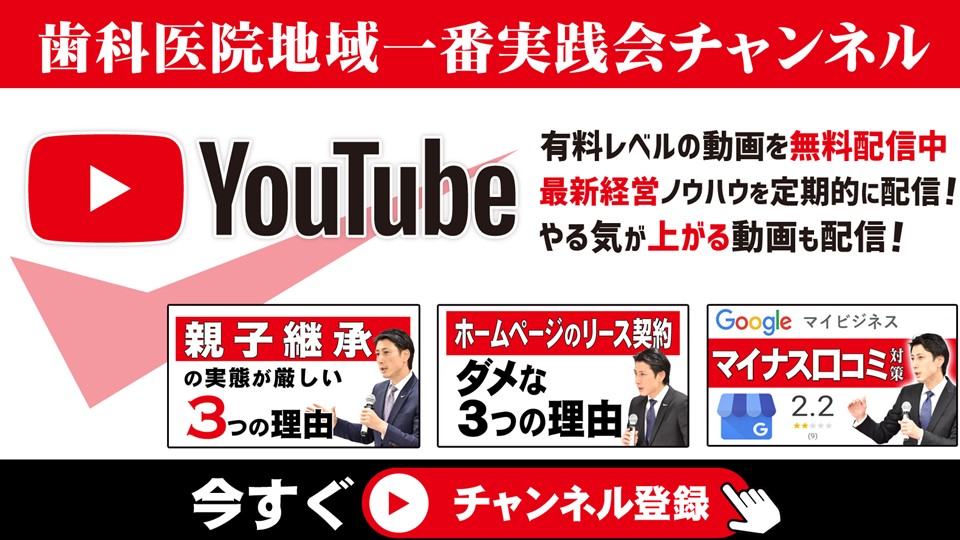このブログは約 15 分で読めます
実践会ブログを御覧の皆さん、
こんにち(ばん)は。歯科医院地域一番実践会の染谷です。
建設的な議論を生む3つの視点とか仰々しいタイトルを付けちゃいましたが、「うちの医院(チーム)、会議しててもなんでか意見が出にくいんよなぁ…」なんて、
世の院長先生や、チームを率いる幹部スタッフの方々なら、一度や二度でなく、場合によっては毎回そう感じているのではないでしょうか?

たとえば、会議で「何か意見はありますか?」と問いかけても、シーンと静まり返る。ようやく誰かが口を開いても、「それは難しいんじゃないかな」と否定的な声が上がり、そこで話が終わってしまう。
同じ目標に向かって進むべきチームなのに、なぜこんなことが起こってしまうのか?
今回は、チームがもっと活発に意見を出し合い、前向きな話し合いができるようになる、つまり建設的な議論を生み出すための3つの視点について考えてみました。
「もっとチームから意見が欲しい」「会議を活性化させたい」と悩みに悩んでいるナヤンデルタール人なみなさんや、会議の進行役をしなければいけない方は、ぜひ読んでみて、参考にしてみてください。
なぜ、チームは「言いにくさ」を感じてしまうのか?
「うちのスタッフは積極性がないな」「もっと考えて発言してほしい」
そう感じたことはありませんか?いやコンサルしていてほとんどがこんな感じです。
しかし、それってその人だけに原因があるのでしょうか??
つまりメンバーが意見を言わないのは、個人の性格や意欲だけの問題ではないかもしれません。
実は、会議の雰囲気やチームの文化が「言いにくさ」を生み出しているケースも非常に多いのです。
では、具体的にどんな要因がメンバーの口を閉ざしてしまうのでしょうか?
- 「発言していいのかわからない」という不安:
自分の意見が歓迎されるのか、そもそも発言する場が設けられているのかが不明瞭だと、人はためらってしまいます。特に若手スタッフや新しいメンバーは、この傾向が強い - 「否定されるのではないか」という恐れ:
これが一番多い気がします。せっかく勇気を出して発言しても、頭ごなしに否定されたり、批判されたりする経験があると、次からは意見を出すのが怖くなってしまいます。
そもそも、横からみていてリーダーや院長の意見も結構間違っていることも多いのにあたかもそれが正しいかのように否定する。 - 「意見が活かされない」という徒労感:
これも多い。苦労して出した意見が、結局何も採用されなかったり、その後どうなったのかフィードバックがなかったりすると、「言っても無駄だ」と感じてしまいます。これでは、発言する意欲はどんどん失われていきますよね。ね。
私自身も、1社目は会議に参加したら絶対に発言しないといけない会社で、発言しない奴は価値なし、と育てられましたが、
とはいえ社会人になりたての頃は「こんなこと言っていいのかな?」「的外れな意見だと思われたら恥ずかしい」と、発言をためらうことがよくありました。
このように、多くの人が「場の空気を読んで出方をうかがう」経験をしているのではないでしょうか。
意見を言わないのは、彼ら彼女らが何も考えていないから、だけではないのかもしれませんね。
むしろ、チームの雰囲気や仕組みが「意見を言いにくい環境」を作り出してしまっている可能性が高いのです。
この「言いにくさ」の根源を理解することが、建設的な議論を促す第一歩となります。
「未完成」を歓迎する文化を築く:議論を前に進める「たたき台」のという視点
「提案は完璧であるべき」――そんな固定観念にとらわれている医院が多い??
そもそも、事前に考えてきてね、というのも早くて三日前。前日にいう院長、幹部もいるのが現実。
そんな中で、完璧なものが出るはずもない。てか、1か月前に言っても、日々の診療があって、どこかで忘れてしまって…で考えていないです。
にもかかわらず、会議での議論では、「もっとちゃんと考えてきてください!!」いやいやちゃうで。
むしろ、「たたき台」としての提案こそが、議論を加速させ、チームを前進させる起爆剤となるのです。
考えてみてください。まだ方向性が定まっていない段階で、「何か良いアイデアありますか?」と漠然と問われても、何をどう考えれば良いのか、戸惑ってしまう。
そんな時、誰かが「例えばこんなのはどうでしょう?」と、たとえ未完成でも一つ案を出してくれたらどうでしょう?
その案を基に「それなら、こうしたらもっと良くなるかも」「いや、むしろこっちの方向性の方が…」といった具合に、比較検討やブラッシュアップが始まり、議論は一気に具体性を帯びていきます。
未完成な意見でも大歓迎という空気を作るためには、以下の2点を明確に伝えることが重要です。
- 議論の前提を共有する:
「この時間は、〇〇について、ざっくばらんに意見を出し合うのが目的です」と、会議の目的を冒頭で明確に伝えましょう。これにより、参加者は「完璧な答えを出す場ではない」と認識し、安心して発言しやすくなります。 - 参加者に求める姿勢を明確にする:
「正解があるわけではないので、経験や立場に関係なく、思いついたことを何でも教えてください」と付け加えることで、「どんな意見でも価値がある」というメッセージが伝わります。
役職や経験の有無に関わらず、全員が安心して発言できる心理的安全性を醸成することに繋がります。
「たたき台」を歓迎する文化を育むことは、チーム全体の思考を活性化させ、より良い結論へと導くための鍵となります。
皆さんの医院・チームでも、ぜひ「未完成なアイデア」の価値を再認識し、積極的に引き出す仕組みづくりを始めてみましょ。
提案の「意図」を読み解く:安易な否定が議論を殺すという視点
会議でスタッフから出された意見に対し、「それは少し違うな」「現実的ではないだろう」と感じることは少なくないかもしれません。
しかし、そこですぐに否定の言葉を口にしてしまうと、その瞬間に議論は停止し、意見を出したスタッフは「言わなければよかった」と後悔してしまうことになります。
例えば、こんな場面を想像してみてください。
ミーティングで、「どうすればもっと多くの患者さんに当院を知ってもらえるか?」について話し合っているとします。その時、一人の歯科助手さんが「ほなInstagramでの情報発信を強化してみてはどないでっしゃろか?」と提案しました。

この時、もし院長先生や幹部スタッフが「いや、SNSは若い人向けやろ?」「うちは高齢の患者さんが多いから合わへんのちゃうか?」「投稿を作る時間もあらへんし、スタッフの手間ばかり増えるんちゃうか?それで効果でえへんかったら。。。」と即座に否定してしまったらどうなるでしょう?
おそらく、その後の議論は沈滞し、他のスタッフも発言をためらうようになってしまうでしょう。
でも、もしその歯科助手さんの提案の背景に、「最近、新患の数が少し減っている気がする」「既存の患者さん以外にも、若い世代や子育て世代にも当院の良さを知ってほしい」「ウェブサイトだけでは、気軽に情報に触れてもらう機会が少ない」といった潜在的な課題意識があったとしたらどうでしょうか?
表面的な提案内容だけでなく、その裏に隠された「なぜそう提案したのか?」という意図や課題に目を向けることが、建設的な議論を深める上で非常に重要になります。
提案というものは、多くの場合「この課題を何とかしたい」「うまく言葉にはできないけれど、何かもやもやする」といった、根底にある課題意識や思考から生まれてくるものです。
表面的な提案内容だけを見るのではなく、その背景にある課題に目を向けることで、「その課題に対しては、Instagramだけでなく、他にもっと良い方法があるかもしれない」「様々な手段を視野に入れて、根本的な課題解決策を検討していこう」といった、より前向きで建設的な話し合いへと繋がります。
安易に手段の良し悪しを判断してしまう前に、まずは「なぜその提案が出てきたのか?」という背景、つまりスタッフが抱える課題意識に深く注目するようにしましょう。
なのでチームの議論をさらにスムーズに進めるための一言としては、
「この案が生まれた背景や、解決したいと思った課題について教えてもらえますか?」
「その課題に対して他にどんな解決手段があるか、さらにアイデアを出し合いましょう」
とかがいいのかな?
こういった問いかけによって、スタッフは安心して自身の課題意識を共有でき、チーム全体で多角的な視点から解決策を探る協力的な姿勢が生まれるような気がします。
「その後」を共有する:意見の「価値」を最大化するフィードバックという視点
せっかく貴重な意見を出してくれたのに、「あの話、結局どうなったんだろう?」と、その後の進展が見えない状況が続くと、チームメンバーは次第に「言っても意味がないのかも…」と感じるようになってしまいます。

意見の採用・不採用にかかわらず、議論に参加していたメンバーには、その後の動きを共有するのがいいでしょう。
この共有こそが、参加メンバーの発言意欲を維持し、さらに高めるための重要なステップとなります。
- 意見を採用した場合:
提案者の意見が実際に活かされ、良い結果に繋がった際には、その具体的な成果や周囲からの評価を伝えましょう。「〇〇さんの提案を取り入れた結果、患者さんからこんな嬉しい感想をいただきました!」「問い合わせが〇%増えました!」など、目に見える形でフィードバックすることで、提案者は「自分の意見がチームに貢献できた」「価値を生み出せた」という大きな自信と達成感を得ることができます。
これは、次の積極的な発言への強力なモチベーションとなるでしょう。 - 意見が見送られた場合:
残念ながら採用に至らなかった場合でも、決してそのままにせず、「なぜ今回は見送ることになったのか」という理由を明確に伝えましょう。さらに、「今後、どのような状況であれば活かせる可能性があるか」「別の機会で検討するために、ドキュメントに残しておこう」といった前向きなフィードバックをすることで、提案者は納得感を得られ、自分のアイデアが無駄になったと感じることはないのかな~と思います。
「自分の声がチームに届いている」「自分の意見が真剣に検討されている」という実感が、メンバー一人ひとりの「次なるアイデア」や「積極的な意見」へと繋がっていきます。
このように具体的な共有とフィードバックを通じて、歯科医院のチーム全体が「意見を出しやすい」「意見が活かされる」という好循環を生み出し、より良いクリニックづくりへと繋がるのだと思います。
「意見を出しやすいチーム」が、歯科医院の未来を拓く(と思う)
「意見を出しやすいチームをつくる」と聞くと、「ただ仲が良いだけの馴れ合いの集団を目指すのか?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、私たちが目指すのは決してそうではないですよね?
同じ目標に向かう歯科医院のチームとして、妥協することなく、常にベストな診療や運営方法を模索していく。そのためにこそ、スタッフ一人ひとりが自分の考えを安心して話し合える「土台」を築くことが重要だと思います。
これは、コンサルに行っていて思うことなのですが、まず院長や幹部が一人のビジネスウーマン、ビジネスマンとして見ていない。どこか子供を相手にしているような気がします。
対価が発生している以上、仕事をするメンバーとしてみなければいけないし、そのように育てないといけないのです。
そのためには「仕事とは」という考え方もとても重要になります。
こういった土台を作るために弊社は
新人スタッフ研修 https://www.consuldent.jp/seminor/shinjin.html
新人スタッフ育成塾 https://www.consuldent.jp/seminor/ikusei.html
などのセミナーを用意しているのです。ただ、社会人になり実践を積むだけでは、やはり難しい。だからこそセミナーに出して終わり、ではなく、その後仕事を一緒にするメンバーとしてかかわる必要があるのです。
そして、もし院長先生や幹部スタッフがすべてを判断し、他のメンバーは与えられた業務をただこなすだけ、という状態が続いてしまったらどうでしょう?
そのチームは、残念ながらリーダーの実力や視野以上に成長することはないのです。
実際にコンサルティングを行っていて、意外と面白い種のような話をしてくれる1年目もかなりいます。
「早く行きたければ一人で行け、遠くへ行きたければみんなで行け」なのかなと思います。
多種多様な視点やアイデアが活発に飛び交う建設的な議論ができれば、きっと今の歯科医院を、もっと先の未来へと導くことができるはずです。
今回の記事が、皆さんの歯科医院がそんな「遠くまで行けるチーム」を築き上げるための、ささやかなヒントとなれば幸いです。