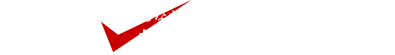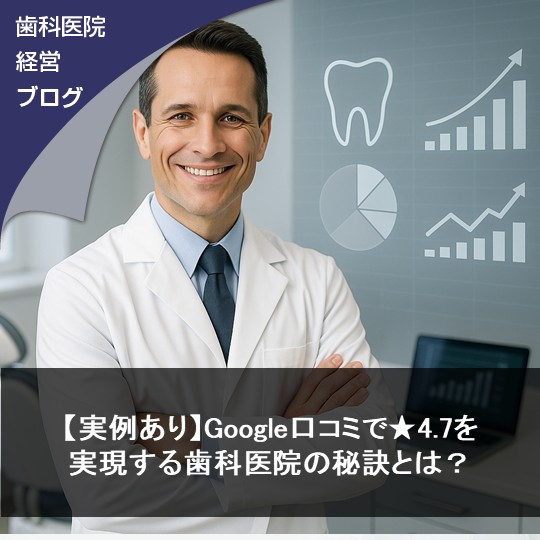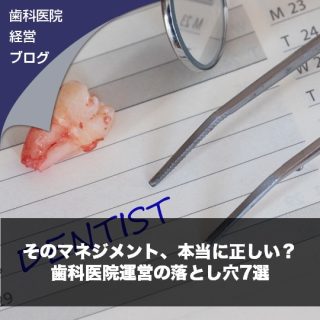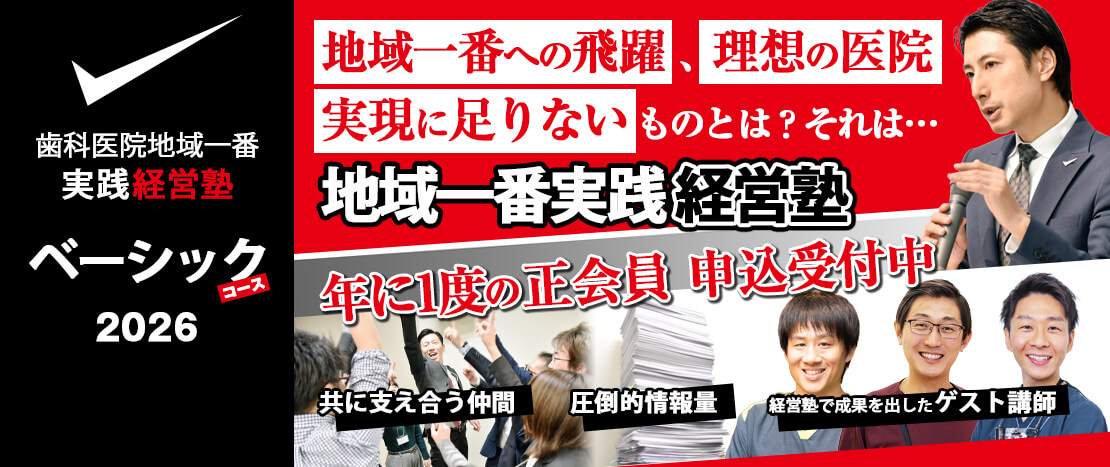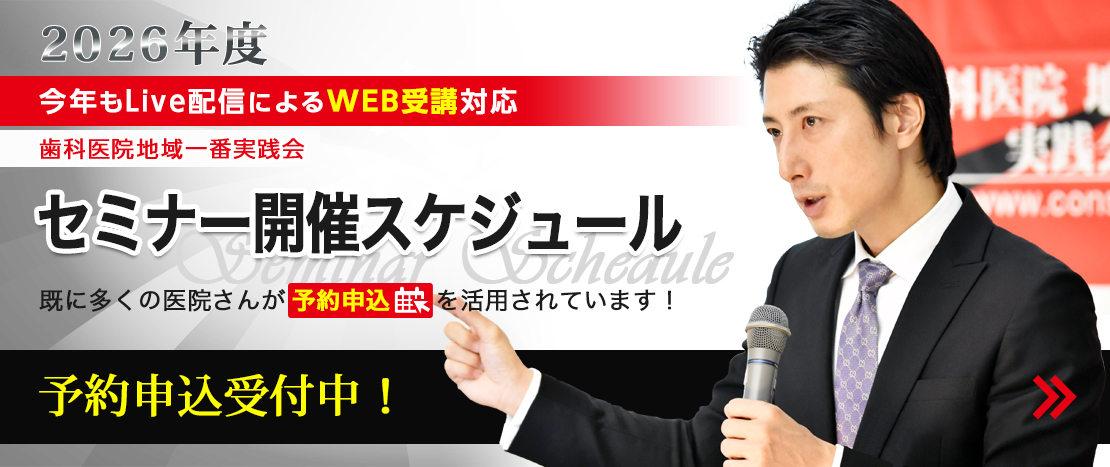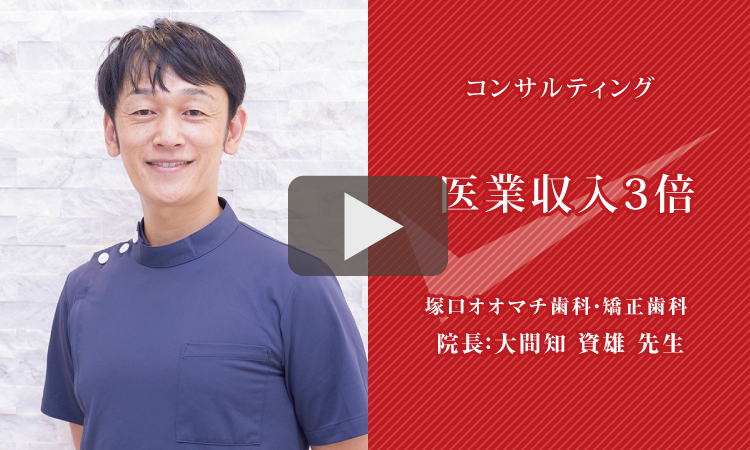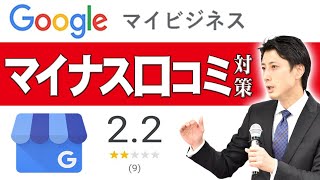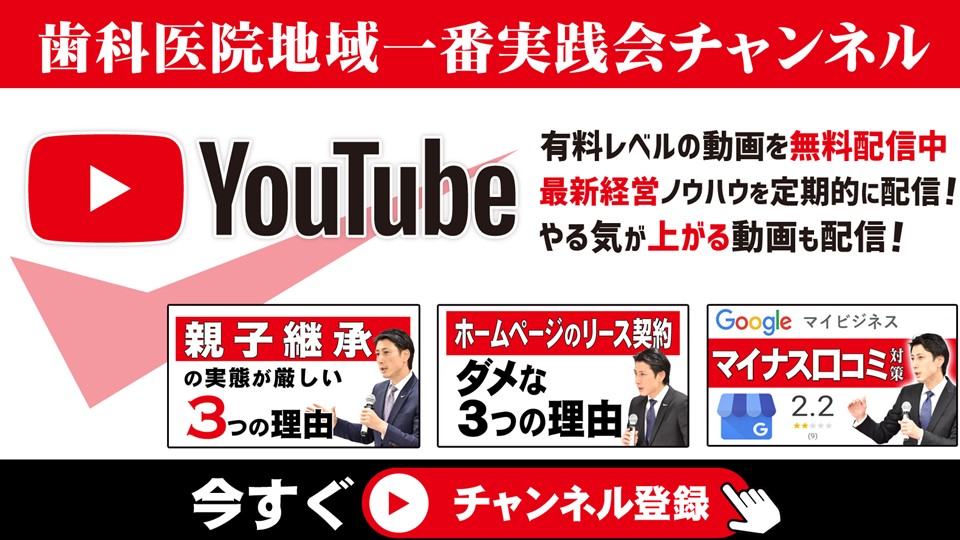このブログは約 17 分で読めます
皆さん、こんにちは!
歯科医院地域一番実践会のコンサルタント、滝沢です。
「最近また★1がついた…」
「スタッフに口コミお願いしてって、なかなか言いにくいんですよね…」
そんな声を、院長先生からよくお聞きします。
すでに多くの医院で、Google口コミの重要性を理解し、対策に取り組んでいる医院様も増えてきました。
一方で、
「必要性はわかっているけど、なかなか本格的に取り組めていない…」
「少し試してみたけど、うまくいかなくてやり方に迷っている…」
と感じている医院様も、実際には少なくありません。
このブログでは、
✅ これから口コミ対策に本格的に取り組みたい方
✅ 少し試してみたけどうまくいかず、やり方に迷っている方
そんな医院様に向けて、自然に口コミが集まり、患者さんから“応援される医院”になるための実践的なヒントをお伝えします。
口コミ評価★4.7をキープする医院の共通点や、数ヶ月で新患数が倍増した成功事例も紹介しながら、
「お願いの仕方」と「空気づくり」の工夫について、明日から使える形でご紹介していきます。

【現状】口コミが少ない医院に起きている3つの機会損失
もちろん、先生方はすでにご存じかとは思いますが、念のため、今なぜGoogle口コミがこれほど重要なのかを改めて整理しておきます。
今や多くの患者さんが、来院前にスマホで「地域名 歯医者」と検索し、地図とともに表示される口コミ評価やレビュー件数を見て医院を比較・検討しています。
評価の高さやレビューの内容は、信頼できそうかどうかを判断する重要な材料として機能しており、
口コミは“あった方がいい”ではなく、“なければ選ばれない”時代になりつつあります。実際に、美容室や飲食店などは口コミを見て判断する方も多いのではないでしょうか?
こうした時代背景を踏まえると、口コミが少ない状態で放置されていること自体が、大きな経営リスクといえます。
以下の3つは、実際に多くの医院で起きている機会損失の代表例です。
- 信頼感を与えられない
どれだけ技術が優れていても、口コミがほとんどない医院は「選ばれる候補」にすら上がらないケースがあります。
患者様にとって、実際の診療内容は見えないからこそ、「他の人がどう感じたか」が判断の基準になります。
口コミが少ないだけで、“不安”や“疑念”を与えてしまう原因になってしまい、非常にもったいないなと思います。
- Google検索での表示順位が上がりにくい
Googleビジネスプロフィールでは、口コミの件数と評価の高さが検索結果の表示順位に影響を与えます。※それ以外の要素もあり
口コミが少なければ検索上位に出てこない=見つけてもらえないという致命的な課題につながります。
- 紹介・リピートのきっかけを逃しやすい
口コミが多い医院は、「通ってよかったから人にも勧めたい」といった患者さん自身の紹介意欲を後押しします。
一方で、口コミが少ないと、どれだけ患者満足度が高くても「人に教えたい」と思われるきっかけが弱くなり、再来院や紹介の連鎖の機会損失となり、新患獲得にはなかなかつながりません。
このように整理してみると、口コミは単なる「評価」ではなく、「信頼・認知・集患力を左右する“経営資産”」として位置づけてもよいくらい重要な項目かと思います。
取り組みの遅れが、じわじわと新患数やリピート率に影響してくる――そのことを改めて意識しておきましょう!
【実践法】★4.7をキープする医院に共通する5つの仕組み
では、実際にどのように口コミを増やしてるのか??私が担当する医院様で実際に行っている例を参考に、口コミが自然と集まり、高評価をキープしている医院のいくつかの「共通する“仕組み”」をご紹介していきます!
Step① そもそも「なぜ口コミを依頼するのか?」を全員で共有する
まず最初に大切なのは、スタッフ全員が「なぜ口コミを依頼するのか」を理解しているかどうかです。
「患者さんのために頑張っているのに、なぜ“お願い”しなきゃいけないの?」
「営業っぽくて苦手…」
「忙しくて声掛けする暇なんてないです!」
そんな抵抗感を持つスタッフさんも少なくありません。
だからこそ、院内ミーティングなどで
- 口コミが医院の信頼をつくる
- 自分たちの努力を“見える形”で伝える手段になる
- 医院の未来を患者と一緒に育てていく取り組みである
- 医院選びで悩む患者様に、参考になる情報を届ける
といった意味づけを丁寧に共有し、納得してもらうことがスタート地点です。
口コミに限らず、意味付けはとても大切なので、忘れずに実施していきましょう!
Step② 口コミ依頼の「タイミング・担当・トーク」を明確に決める
口コミ依頼を成功させるカギは、属人的にせず医院全体でルール化することです。
- いつ:診療後?会計時?
- どこで:チェアサイド?受付?
- 誰が:担当医?衛生士?受付?
- どんな言葉で?:トークを用意
トーク例
スタッフ:
「〇〇さん、今日で〇〇回目ですね!いつもちゃんと通ってくれてありがとうございます!
そんな〇〇さんにぜひお願いしたくてお声がけさせてもらいました。」
患者さん:「えっ、なんですか?(笑)」
スタッフ:
「最近、口コミを見て来てくださる方が増えてきてて。
でもやっぱり、どんな雰囲気なのかって、実際に通っている方の声が一番伝わるんですよね。だから、〇〇さんみたいに長く通ってくださってる方の言葉が、すごくありがたくて…
もしよければ、他の患者様のためにも、ぜひ口コミを書いていただけませんか?」
患者さん:「あ、全然いいですよ!書きますね。」
スタッフ:
「ありがとうございます…!こちらのQRコードを読み取って頂くと、スマホでパッとできます。この後、待合室で書いてくれると嬉しいです!」
このように、「いつ・どこで・誰が・どのように」を明確に決め、スタッフ全員で共通のやり方で声かけができるようにしておきます。
さらに、「誰に声をかけるか?」をあらかじめ決めておくこともポイントです。
院長先生やスタッフさんからみて「この患者さんなら、きっと良いことを書いてくださる」と思える方をピックアップし、来院予定の当日は朝のミーティングなどで対象者を全員で確認・共有することで、確実に声掛けをできるようにしていきます。
Step③ ツールを準備して“投稿の壁”をなくす
「書いてほしい」とお願いするだけでは、患者さんはなかなか動いてくれません。
先程のトーク例にも出てきましたが、大切なのは、スムーズに投稿できる環境=“仕組み”を用意することです。
- QRコードの準備
Googleレビュー投稿ページへ直接アクセスできるQRコードを用意し、印刷しておき、すぐに見せられるようにしておく。もしくは、チェアサイドや待合に配置しておくなど - アカウントがない方への対応
Googleアカウントを持っていない方もいらっしゃるので、どのように登録するか?をまとめた説明用紙を用意しておく。または、その場では無理に案内しない。
などのルールを決めておくことが大切です!
- 名前表示を気にする方への配慮
実名で登録している方は、名前が表示されてしまうので、不安な患者様へは登録名の変更方法の説明用紙もあると慌てず対応ができます。
こうした準備を事前に整えておくことで、“書きたかったけど書けなかった”を防ぎ、自然な投稿が生まれる導線をつくれます。
Step④ 決めたトークをロープレで練習する
決めたトークや流れを、現場で自然に使いこなすためにはロールプレイングによる反復練習が効果的です!
- スタッフと患者様役に分かれて、現場を想定して練習
- 「診療しながら」「会計の混雑時に」など、リアルな状況を再現
- 院長やリーダーがフィードバックし、言い回しやタイミングをブラッシュアップ
こうしたトレーニングを通して、“スクリプト通り”から“自然な声かけ”へ進化させていきます。
はじめは緊張するかもしれませんが、何度か練習をしておくとスムーズに声掛けができるのでオススメです!
Step⑤ 口コミ文化を“院内に根付かせる”
口コミは“集めて終わり”ではありません。
投稿された内容をスタッフ全員で共有し、モチベーションや行動改善につなげることが大切です。
例:「今月は◯◯さんが口コミを書いてくださいました。“受付が丁寧”と書かれていました!」
このような共有を続けることで、
- 「自分たちの仕事はちゃんと見られている」
- 「また良い印象を持ってもらえるように頑張ろう」
という意識が自然と芽生え、サービスの質の向上 → 良い口コミがさらに増えるという好循環が生まれていきます。
この5つのステップを段階的に整えていくことで、無理なく・自然に・継続的に良質な口コミが集まり、★4.7以上の高評価をキープする基盤ができあがります。
次にご紹介するのは、実際にこれらの取り組みを行い、口コミ数が15倍、新患数が5倍になった地方医院様のリアルな成功事例です。

【成功事例】口コミ数アップで新患が5倍に増えた地方医院の取り組み
ここでは、実際に口コミ対策を強化したことで、わずか1年で新患数が5倍に増加した地方歯科医院の成功事例をご紹介します。
▼Before
- 口コミ数:3件
- 評価:★3.2
- 新患数:月5〜8名
この医院様は、地方にあるチェア4台の地域密着型歯科医院。
お子様からご年配の方まで幅広い患者層が通う、アットホームな雰囲気の医院でした。
当時は「患者満足度は高いはずなのに、新患が伸びない」という悩みを抱えており、Google口コミはたった3件、評価も★3.2。
検索結果でも目立たず、MEO対策を早急に進めて行く必要がありました。
▼After(取り組みから1年後)
- 口コミ数:46件(約15倍)
- 評価:★4.8に改善
- 新患数:月35〜40名に急増(約5倍)
しかもこの結果は、リスティング広告などの有料施策は一切行わず、口コミ対策のみに集中した成果です。
実施した主な取り組み
- 口コミの必要性をスタッフ全員で共有
口コミが医院の信頼を育てるものであることを院長自ら説明し、チーム全体の意識づくりからスタート。 - 声かけのルールと対象者の事前共有
「この方なら書いてくださるかも」と思える患者さんを前日のうちにピックアップし、当日の朝礼で全員で確認して声かけのタイミングを統一。 - QRコードのチラシと導線づくり
Googleレビュー投稿用QRコードチラシを作成し、患者さんがスマホですぐ投稿できる環境を用意。
名前やアカウントの不安がある方には丁寧な案内も実施。 - ロールプレイングでトークを自然にする練習
患者様役・スタッフ役に分かれ、日常業務の流れの中で口コミの声かけが自然にできるように、繰り返し練習。 - 投稿された口コミはミーティングで全員に共有
良い口コミを読んで称賛し合う文化ができ、スタッフのやる気が高まり、医院全体の空気も明るくなった。
これらの取り組みを地道に続けた結果、口コミ数は46件にまで増加、評価も★4.8に改善。
「口コミを見て予約しました!」という新患が急増し、月5〜8名だった新患数は、わずか1年で35〜40名へと急増しました。
他にも、より短期間でより多くの口コミを獲得し、新患アップにつながっている医院様もありますが、あえて現実的な数値の事例を共有させて頂きました!
この事例からもわかるように、「特別な技術」ではなく、“誰でもできる基本の徹底”が、大きな成果を生むということです。
地方であっても、チェアが4台でも、口コミを通じて*“選ばれる医院”に変わることはできる。そう信じて、まずは実践することが大切です。
【注意点】医院の“空気づくり”が伴っていなければ効果は出にくい
ここまでご紹介してきた口コミ対策は、多くの医院で成果を上げている実践法ですが、すべての医院で“魔法のように効果が出る”わけではありません。
特に、
- スタッフの表情が暗い
- 院内にピリピリした空気が漂っている
- 忙しさや不満が蓄積していて、余裕がない
といった状態では、どれだけ仕組みやトークを整えても、患者さんには「お願いされている空気」だけが伝わってしまいます。
つまり、口コミ対策を本当に機能させるには、日常の雰囲気やチームの在り方こそが土台になります。
「無理にお願いする」のではなく、
「この医院を応援したい」
と思ってもらえるような関係性が築けているかどうか――
これが、口コミが“自然に増える医院”と、“形だけやっても成果が出ない医院”との大きな違いです。
また最近では、企業による「やらせレビュー(ステルスマーケティング)」がニュースで取り上げられる機会も増えてきました。
これに関連して、Googleの口コミ規約も厳しくなっており、
- プレゼントや特典と引き換えに口コミを依頼する
- 実際に来院していない人に口コミを依頼する
といった行為はポリシー違反に該当し、アカウント停止や口コミ削除の対象となるリスクがあります。
口コミは“自主的な応援の声”であることが前提です。
医院の信頼を損なわないためにも、誠実な方法で地道に積み上げていくことが、最終的には一番の近道です。
【まとめ】口コミは「お願いの質と空気づくり」で決まる
口コミは、ただ「書いてください」と言うだけでは増えません。
でも、“応援したくなる医院”を目指して、仕組みと空気の両方を整えていけば、自然と患者さんが声を届けてくれるようになります。
そしてその声は、医院の信頼となり、選ばれる理由となります。
「最近★1がついてしまった…」
「お願いしても書いてもらえない…」
そんな悩みがあるときこそ、今回ご紹介したような仕組みをひとつずつ院内に落とし込んでみてはいかがでしょうか?

まずはできるところから、たとえば
✅ 朝礼で「誰に声をかけるか?」をスタッフと共有する
✅ QRコード付きのチラシを作成する
✅ 口コミをミーティングで読んでみる
小さな一歩が、大きな変化につながっていきます。
患者様に「この医院にはずっと通いたい」「誰かに勧めたい」と思ってもらえること。
それこそが、★4.7の評価を支える最大の仕組みです。
口コミ対策は、単なる集患のテクニックではありません。
それはむしろ、「医院の信頼・文化・チーム力の“見える化”」だと私は考えています。
口コミが自然と集まる医院は、やはり日々の診療やチームづくりに真剣に向き合っているところばかりです。
「技術」だけでなく、「人の想い」が患者さんに伝わっているからこそ、応援の声が生まれるのだと思います。
今回ご紹介した内容は、決して難しいことではありません。
ただし、“続ける覚悟”と“院長のリーダーシップ”が必要です。
ぜひ、先生の医院に合った方法で、できるところから始めてみてください。
先生とチームの取り組みが、医院にとって一生残る信頼資産となることを、心より願っております。