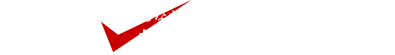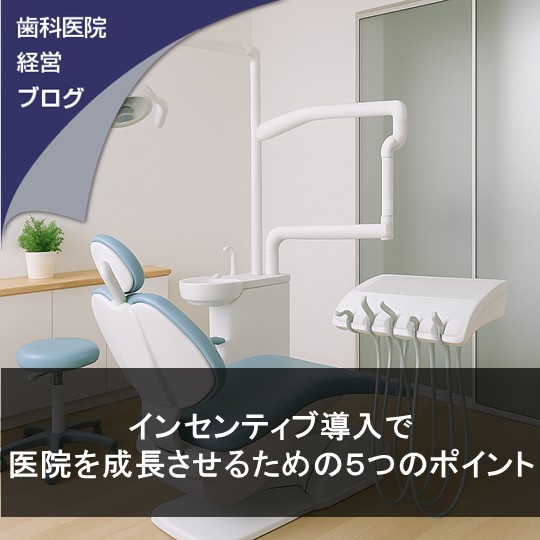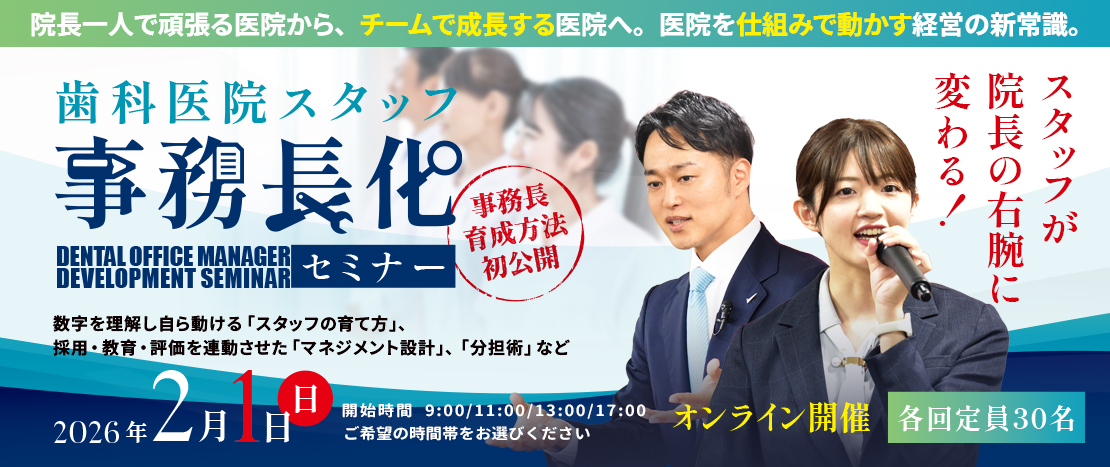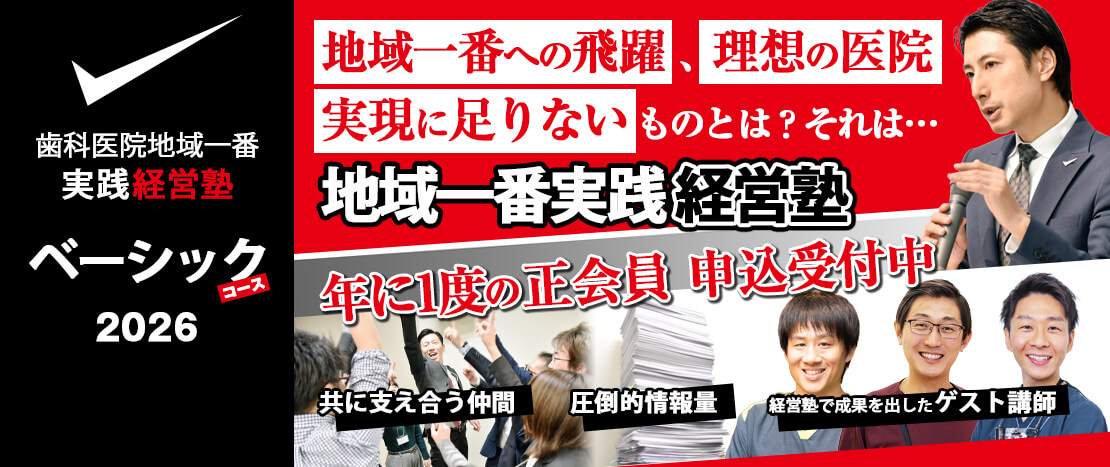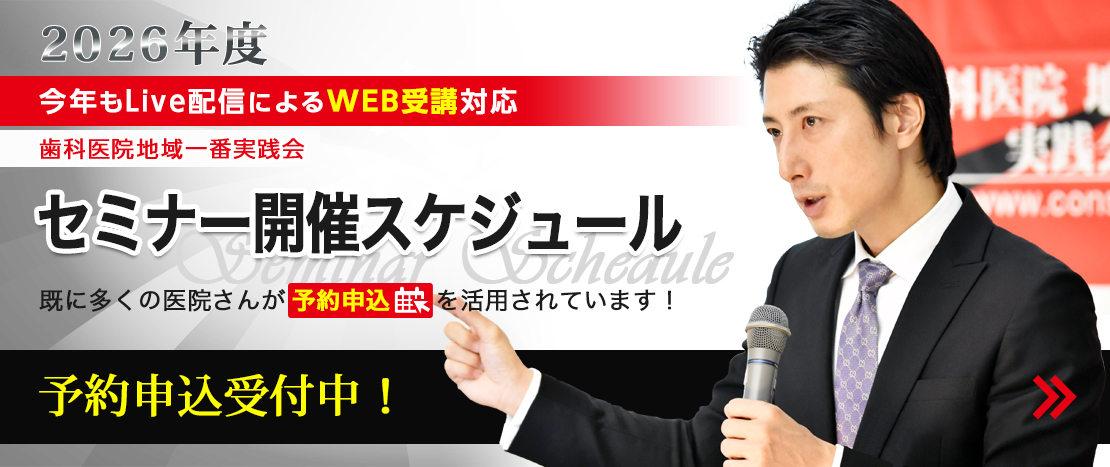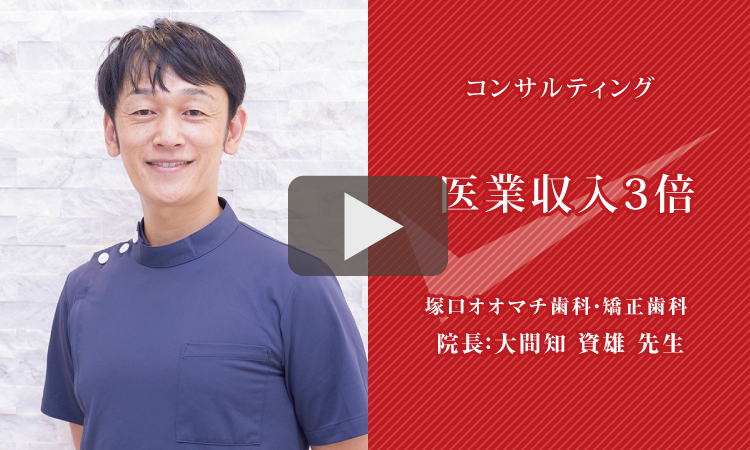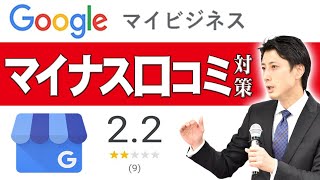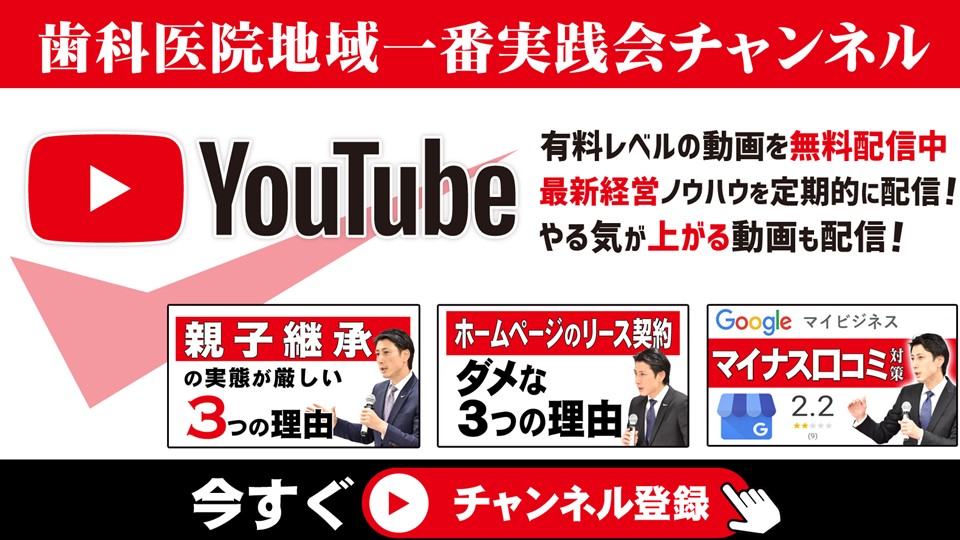このブログは約 7 分で読めます
はじめに
こんにちは、経営戦略研究所コンサルタントの渡邊です。
今回はご相談いただく機会が増えている「衛生士の個別のインセンティブの導入に関して」お伝えしてまいりたいと思います。
衛生士さんの頑張りを正しく評価し、やる気を引き出すためにインセンティブ制度を取り入れたことでメンテナンス人数が増え、医業収入が大きく伸びた成功例は少なくありません。
実際の弊社コンサルタントの山ノ内が以前ブログでお伝えしている通り、
国の大きな方向性を考えまして、今後の歯科衛生士さんの役割、重要性は
高まってくると考えています。
歯科衛生士の職務充実を骨太方針やモチベーション理論の観点から考える
しかし一方で、「衛生士さんだけが得をしている」「自分の担当の患者さんの業務しかしなくなってしまう」「職種間の不満の元となってしまう」…といった事例も実際に起きています。
インセンティブは使い方を誤ると、組織の分断やモチベーション低下を招く“両刃の剣”なのです。
私自身はインセンティブを強く推奨しているわけではございませんが、衛生士さんの行う予防が非常に重要な役割となってきていることから導入を検討される先生が多くなってきているように感じます。
しかし、それによって人間関係やチームとしての規律が崩れてしまっては全く意味がありません。
では、どのようにすれば人間関係を壊さず、医院全体の成長につながるインセンティブ制度を導入できるのでしょうか。ここでは5つのポイントに整理してお伝えします。

1.幹部スタッフを軸に導入意図を共有する
制度を導入する前に必ず行うべきは、幹部スタッフを巻き込み、医院全体の共通の目的や方向性をそろえることです。
特に尊敬を集める衛生士リーダーや助手リーダーが納得していない状態で進めると、職種間の対立が起こりやすくなります。
幹部ミーティングで院長の考えや狙いを丁寧に説明し、「なぜ衛生士にインセンティブが必要なのか」「医院の医業収入全体への効果」まで理解してもらうことが大切です。
衛生士の頑張りが収入増につながり、その結果他の職種の待遇改善や働き方の改善にも波及するという全体像を共有できれば、不公平感は大きく減ります。
逆に言えばこのようなことを理解出来る土台がなければ導入はしないほうが良いと思います。
2.他職種にも評価と報酬のチャンスを用意する
「衛生士だけ評価される」と感じると、助手のモチベーションは一気に下がります。
そこで有効なのが、助手にもインセンティブや評価ポイントを設定することです。
たとえば以下のような項目です。
TC(トリートメントコーディネーター)としてのインセンティブの支給
院内プロジェクトのリーダーや幹部などを担当することでの手当の支給
後輩教育や研修などのコンセプチュアルスキルの実施を評価する制度
これらの医院全体の職種間の役割やバランスを踏まえた上で幹部会で評価基準を話し合い、衛生士だけでなく他職種の頑張りも報いる仕組みを作ることが、組織全体の一体感を生みます。
3.技術・対応力アップを評価基準に組み込む
インセンティブの支給が定量評価だけに偏ってしまいますと、短期的な成果追求に偏りがちです。
そこで技術力・対応力の向上を評価基準に入れることをおすすめします。
適切な処置や説明で患者様から高評価を得ている
長期的なメンテナンス継続率が高い
院内外の研修参加や資格取得など自己研鑽を行っている
こうした姿勢は患者満足度と医院の信頼向上に繋がっていきます。単なる売上競争ではなく、院内のスタッフからも患者さんからも「尊敬される衛生士像」を浸透させることが、制度の健全運用につながります。
4.算定ルールとデータ管理体制を整える
「どの業務を誰の成果とするのか」が曖昧だと、不満や疑念が生まれてしまいます。
導入前に算定ルールを明確にし、全員が納得できる管理方法を決めることが必須です。
ドクター施術分と衛生士施術分の区分方法
自費・保険の評価方法に関して
記録の方法(レセプト・予約システム・日報など)
このルールを幹部から各スタッフに周知し、透明性を保つことで、制度への信頼感が高まります

5.人件費率とモチベーションアップ両方を意識した設計
インセンティブはあくまで医業収入に対する人件費率とのバランスが重要です。
このような経営的側面を意識せずに設定してしまいますと、個人の状態が良くなっても医院全体の状況が悪くなってしまいます。
人件費率に限らず財務諸表等に表れる数値というのは医院の状態を表しており、適性値や目安がございます。
そのため、人件費率が低ければ良いのかというとそういうわけではありません。
医業収入はより多くの患者様へ継続的に良い治療を行い、満足度を高めていく先の結果であり、医業収入に対する人件費率が低すぎるという場合は現場に無理が起きているという見方をする場合もあります。
採用難の時代が到来していることを考えますと個々のスキルアップや定着率を実現し診療効率を高めていくことで人件費率を下げていき、その余剰分でインセンティブを支給することが重要になってまいります。
また、「今月はもう達成できないから頑張らない」というようにインセンティブをつけることで逆効果となってしまうケースもございます。支給期間や評価サイクルを工夫することが重要です。自費と保険の両方を評価対象に含めることで、保険診療をおろそかにするような偏りも回避する工夫が重要です。
最後に
この仕組みを適切に導入したことで医業収入アップに繋がり、結果としてすべての職種のベースアップを実現出来た医院さんもございます。
制度よりも大切なのは“土台”だと私は考えています。
インセンティブ制度は魔法の杖ではありません。
本当に重要なのは、制度がなくてもより多くの患者様により良い治療を提供したいという思いを共有出来る組織づくりや人づくりの考え方です。
そのようなスタンスがあって初めて、インセンティブが医院全体のモチベーションを押し上げるプラスのエネルギーになります。
もし「制度は導入したいが、人間関係や運用が不安」という場合は、まず幹部層との対話と基準作りから始めてみてください。
全員が納得できるルールを作り、職種間の尊敬と感謝を育むことができれば、インセンティブは強力な成長エンジンになります。
医院経営における制度設計や人材マネジメントでお困りの際は、ぜひご相談ください。